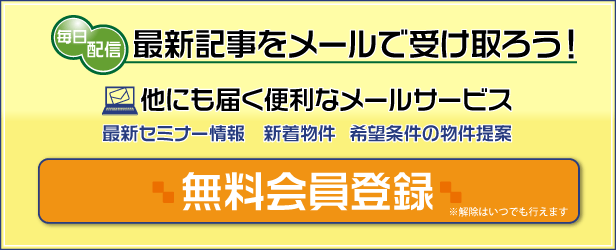戸建てであれば、資金も少なくて済み、物件は豊富で、初心者にも取り組みやすいだろう。そこで、戸建てで高齢者向きアパートのようなビジネスモデルができないか考えてみた。
■ 真っ先に思い浮かぶ「 シェアハウス 」
戸建てを部屋単位で貸し、リビング・キッチンやバス・トイレは共用部として利用する。共用部ではコミュニティが期待できる。賃料はアパートより割安にできるし、水道光熱費も入居者が個別契約するよりは割安にできる。
1階の部屋は高齢者、2階は若い人やシングルマザーに入ってもらえば、多世代居住が実現し、お互いにメリットが出る。しかし、シェアハウスは「 寄宿舎 」に該当し、普通の戸建てを転用するには「 用途変更 」が必要だ。
確認申請が必要でない場合でも、法的規制のクリアや、消防・自治体との調整もあり、結構な手間と労力が必要だ。
■ URの「 ハウスシェアリング 」という考え
シェアハウスは用途変更やハード面での投資などで、参入障壁がある。しかし、URはハウスシェアリングという考えを導入している。これはシェアハウスではないという。
URのホームページには「 家族だけでなく友達同士でもひとつの物件にお住まいいただけます。これをハウスシェアリングと言います 」とある。
参照:http://www.ur-chintai-info.com/feature/detail_05.html
ひとつの物件でシェアハウスと同じように、複数の人が住むことが可能という。この考えを戸建てに適用すれば、ひとつの建物に複数の高齢者が生活できる「高齢者向きハウスシェアリング」が合法的に可能となるはずだ。
■ メリットも大きい高齢者向きハウスシェアリング
高齢者向きハウスシェアリングが成立すれば、数々のメリットが享受できる。最大のメリットは「 孤独死がほぼゼロになる 」ことだ。大家としても心配で、大きな社会問題となっている孤独死問題が解決できる。そのほかにもメリットは多い。
・少ない自己資金で事業が開始できる
・戸建てとして貸すよりは家賃収入が増え、高利回りになる
・「 事業 」として融資を受けることで、資金調達が容易になる
・事業がうまくいかなくなった場合は「 戸建て 」として貸したり、売却することで撤退が可能
・コミュニティや、割安な水光熱費・家賃など、シェアハウスのメリットが享受できる
・長期入居や多世代居住など、高齢者向きアパートのメリットが享受できる
・住まいに困っている高齢者は多いので、今のところ客付けは容易
・空き家を活用すれば、空き家問題の緩和になる
■ 想定される問題点
もちろん、メリットばかりではない。問題点も想定される。大前提として、アパートより規模が小さいので入ってくる家賃の「総額」が少ない。アパートに比べ、家賃は少なくて手間はかかることになる。
それ以外にも、入居者間のトラブル、共用部分の管理などシェアハウスと同じ問題点が想定される。一般的なシェアハウスと大きく違うのは「 高齢者 」ならではの問題点だ。
第3話にその概要と解決策を示したが、ハウスシェアリングでは4、5の問題は無くなるとみていいだろう。
転倒防止や日々の生活のための工夫が必要だったりするが、多くの高齢者にとって「 バリアフリー 」は必須ではない。手すり設置や、段差の緩和・明瞭化で対応できることが多い。第5話の手法でほぼ解決可能だ。
火災時のリスクもある。これは第3話の手法で緩和可能だ。出火原因の3割を占めるストーブ・コンロを廃止すれば、出火を減らすことが可能だ。
音声タイプの煙感知器採用・石膏ボード追加による難燃化・2方向避難路確保などで避難しやすくすれば被害緩和が可能だ。避難時には入居者同士での助けあいも期待できる。
認知症や徘徊などのリスクも想定されるが、これらの心配のある人や、そのような状態になった時は老人ホームや、特養を利用していただくことにすればよい。
理想は終の棲家だが、すべての人の終の棲家である必要はなく、そういう状態になった時は「 専門 」の施設を活用する。そういう考えでいい。そこは住み分けをすることで、社会的コストの削減が図れるはずだ。
■ 介護等を提供すれば老人ホームに。FBで情報交換中
ただし、注意すべき点がある。介護、食事、掃除といった「 介護等 」を提供すると「 老人ホーム」 になる。自治体によって判断基準が違うが、入居者の中に「 高齢者 」が居て、介護等を提供すると、老人ホームとなり、届け出なければ違法となるので、注意が必要だ。
メリットの多い高齢者向きアパート&ハウスシェアリング。FBのグループを作って情報交換をしている。実際に稼働に向けて準備を進めているメンバーもいるので、進捗があれば報告したい。