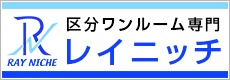前回まで、「 バリアあり― 」の高齢者向きアパートであれば、高齢者は元気に生活できるので、本人も家族も幸せに暮らせる、という内容を紹介してきました。
大家は空室が活用でき、介護事業者は経営上のメリットを享受し、老人ホームを増やさずに済むかもしれない等、そのメリットの多さはすでに述べたとおりです。
では、高齢者が安心して生活できる部屋、「 バリアありー 」の部屋は、どのように実現すればいいのでしょうか?その中には、簡単なDIYでできるものも多くあります。今回はそれについて、具体的に説明させていただきます。
※「 バリアありー 」の特徴や効果については、第2話で詳しく紹介しています。ご参照ください。
■ バリアありーの基本と、高齢者向きアパートへの取り入れ方
バリアあり―の基本は、「 段差を認識する 」「 段差を越える 」といった一連の流れをスムーズに行えるようにすることだ。そのために、室内には以下の工夫を実施する。
<段差を認識する工夫>
段差を認識するには、段差そのものを認識する、段差を予感するという切り口が考えられる。段差そのものを認識するには、「 段差の明瞭化 」を行う。段差のある所に色を付ける...
大家は空室が活用でき、介護事業者は経営上のメリットを享受し、老人ホームを増やさずに済むかもしれない等、そのメリットの多さはすでに述べたとおりです。
では、高齢者が安心して生活できる部屋、「 バリアありー 」の部屋は、どのように実現すればいいのでしょうか?その中には、簡単なDIYでできるものも多くあります。今回はそれについて、具体的に説明させていただきます。
※「 バリアありー 」の特徴や効果については、第2話で詳しく紹介しています。ご参照ください。
■ バリアありーの基本と、高齢者向きアパートへの取り入れ方
バリアあり―の基本は、「 段差を認識する 」「 段差を越える 」といった一連の流れをスムーズに行えるようにすることだ。そのために、室内には以下の工夫を実施する。
<段差を認識する工夫>
段差を認識するには、段差そのものを認識する、段差を予感するという切り口が考えられる。段差そのものを認識するには、「 段差の明瞭化 」を行う。段差のある所に色を付ける...
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる