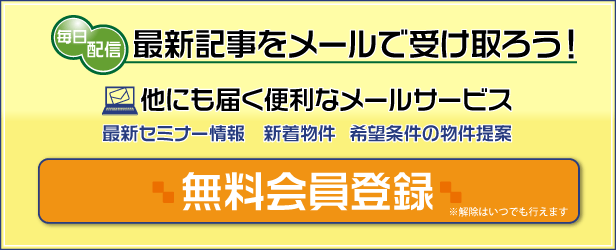参照:間取りを勝手に変えられた!相続対策で建てた初の新築案件で発生した大トラブル(1)
■ 施主検査後のその後について
勝手に間取りを変えられるなど、問題だらけのアパート工事でしたが、業者から、「 完成したから施主検査をしてほしい 」と連絡がありました。見に行くと、とても完成したとは言えない状態です。それ以前に、未解決の問題も多く、私は不信感でいっぱいでした。
施主検査の実施後、この施工業者について改めて調べてみました。すると、以下のようなことがわかりました。
<施工業者のことを調べて分かったこと>
・○○市の土木指定業者をある時期に外されていた
・別の物件でも同様のトラブルを起こしていた(別の工事業者からの情報)
・現場責任者をしていた従業員が退職していた
・事務所の地代を3年間支払っておらず、賃貸人から立ち退き要求をされていた
・○○市の土木指定業者をある時期に外されていた
・別の物件でも同様のトラブルを起こしていた(別の工事業者からの情報)
・現場責任者をしていた従業員が退職していた
・事務所の地代を3年間支払っておらず、賃貸人から立ち退き要求をされていた
業者側は「 完成した 」と言って、残りの代金の支払いを求めてきましたが、今の状態で支払うことはできません。すると、施工業者は反撃に出てきました。
<施工業者が実施してきたこと>
・建物内に入れないようにバリケードを設置し鍵を掛ける
・残代金の請求書が内容証明郵便で自宅に数回届く
・建物内に入れないようにバリケードを設置し鍵を掛ける
・残代金の請求書が内容証明郵便で自宅に数回届く
すでに2,700万円を支払い済みです。初めての新築案件だったとはいえ、大きなトラブルになってしまったことに、私はショックを受けていました。もちろん、残金を支払うことはできません。

ずさんな工事で2階の床はカビだらけで、キノコが生えていた
■ 施工業者から裁判を起こされる
ある日、〇〇地方裁判所から自宅宛てに、施工業者を原告とする訴状が届きました。見ると、施工業者の代理人弁護士は、地元でも有名な札付きの悪徳弁護士でした。遂に来たかという感じでした。
こちらも弁護士を立てて争うことを決意し、仲介会社の社長の紹介で不動産・建築関係の争いに強い弁護士の先生に代理人を依頼することにしました。
■ 裁判の争点
こちら側が裁判の争点としたのは、下記になります。
・間取りが見積時と契約時で施主の許可なく変わっていたこと
・設備が提案時よりも粗悪品で施工されていたこと
・認印を預けていたが、施工業者が施主の許可なく勝手に契約書類に押印したのはおかしい(民法上の白紙委任が成立するのか)
・工事が大幅に遅延し、引き渡しが受けられる状態でなかったこと
・フェンスの設置が外構工事の追加工事として別途請求を受けたこと
・間取りが変わっていたことや施主の要求どおりの施工がなされていないことによる契約の解除、もしくは建物の建て替え請求ができないか
・工事遅延により、入居予定だった賃貸借契約が白紙になったことによる逸失利益が認められるかどうか
■ 裁判中の問題点
そして、裁判が始まりました。その間に困ったことが次々に起こりました。
<融資返済がスタート>
相続税対策のため、この物件について地元の地銀から融資を受けていました。当初3月には完成する予定で融資を受けていたため、返済の開始は4月からスタートしました。
建物の引渡しすら受けていない状態で、裁判もどのくらいの期間が掛かる分からない中で毎月、返済しなければいけないのは、本当につらかったです。仕方なく、他物件の家賃収入で返済していました。
<裁判が解決するまで次の融資を受けられない>
伯父がガンで余命2年であったため、相続税対策を急いでいて次の新築案件も進めていました。ところが、地元の地銀や信金から、抱えている裁判が解決して、その物件が収益物件として回り始めてからでないと、次の融資はできないといわれました。
金融機関としては当然のことだとは思いますが、私にとっては次の融資を受けられないことは頭の痛い問題で、裁判が解決する2年間は苦い思いをしました。
<地元の不動産業者や親戚にバカにされる>
人の噂が広まるのは早いもので、施工業者である〇〇建設と私が係争していることが、地元の不動産業者や親戚にも知れ渡り、私や伯父のことを陰で馬鹿にする人たちが出てきました。
もちろん、同情して味方してくれる人もいましたが、裁判中は地元の不動産業者や親戚たちと顔を合わせたくない気持ちでした。

裁判になった物件の外観
■ 裁判の結果
裁判は長引き、約1年の時間を要しました。そして、裁判の結果が出ました。こちら側が完全敗訴、施工業者側が全面勝訴という結果でした。敗訴の主な理由は以下のとおりです。
①間取りの変更は確かに被告である施主の同意を取っていなかったと判断できるが、それをもって建物の建て替え、もしくは工事契約の解除となる事由にはならない。
②認印だったとしても判子を預けていたことは白紙委任として認められる。また、被告は有資格者であり長く不動産賃貸業を行っており、判子を預けるということの重要性を理解していると考えられるため。
③設備については、設備仕上表の確認書に捺印をしていることから、そのグレードで被告が納得していたと判断できる。
④工事が遅延したのは5日間であり、最終の引渡しが3月末となったのも、被告が追加の外構工事を依頼したことによるものであると判断できるため、遅延損害は認められない。
⑤ブロック塀フェンスの設置が追加工事ではなく外構工事に含まれるという被告の主張は、外構工事費用が100万円としか記載がなく、工事範囲が明確でないが、原告がコンクリート舗装およびカーポート設置を行っていることから、被告の主張は不当と判断するに至る。
⑥工事遅延による賃貸借契約が白紙となった逸失利益については、残代金の支払いと物件の引き渡しは同時履行の関係に立つことから、被告の引渡未了による逸失利益は認められない。
■ こちら側の主張が唯一認められたもの
完全敗訴でしたが、こちら側の主張が一部のみ、認められたものがありました。それは以下の内容です。
工事内訳書にある杭工事費用179万円は、被告が横浜銀行から4,500万円の融資を受けるために、原告が工事見積金額として上乗せして、架空計上したものと認められる。
認められた理由は、「 後で返金する 」という原告との証書があったこと、原告である業者が杭工事を実施した根拠を示せなかったためです。
■ 判決の結果として施工業者に支払うこととなった工事残代金
この結果、「 請負工事代金4,500万-2,700万( 既払金 )+90万( フェンス設置工事 )-179万( 杭工事返還約束金 )+79万( 水道加入金等の立替金 )=1,790万 」を私からこの業者に支払う必要があると確定しました。
この話はこれで終わりではありません。納得のいかなかった私は高裁へ上告することにしたのです。長くなったので次回に続きます。
つづく