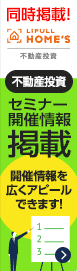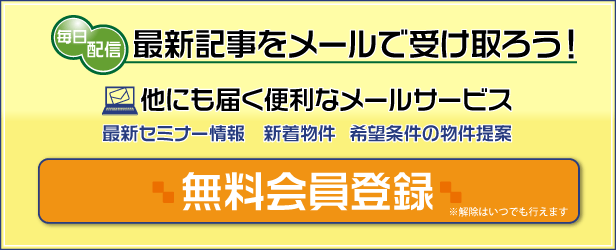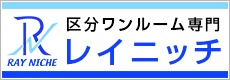今回は不動産の話を。
2012年の民主党から自民党への政権交代以降、紆余曲折はあったもののほぼ一方的に上昇を続けてきた日本の不動産市場。
不動産経済研究所によれば2022年の首都圏新築マンション平均価格は6,288万円と、バブル期を超え過去最高を更新。全国の新築マンション価格も5,121万円と6年連続で過去最高を更新し、10年前と比べると約1,300万年も上昇、とりわけ東京23区では約3,000万円上昇しています。
その理由については「 資材費や人件費の上昇に加え、低金利のなか富裕層や高所得の共働き世帯が都心部の高額物件を積極購入し、高値圏が続く 」「 富裕層や海外投資家の購入意欲が旺盛 」( 日本経済新聞 )などの見立てが一般的ですが、最も大きな要因は「 圧倒的な低金利 」であることはいうまでもありません。
したがって、バブル期と現在の不動産価格水準を比較することにはあまり意味がないと言えます。
■ 不動産の「 価格 」だけを見ても意味がない理由
例えばバブル期の住宅ローン金利は7パーセント超え。一方昨今は固定で1パーセント後半、変動なら0.3~0.4パーセント。最安値はauじぶん銀行の0.289パーセントです。
日銀の政策変更で固定系の金利がやや上昇したものの変動には影響ないどころか、金融機関間の競争原理からむしろやや下がり気味。10年前は固定系ローンの利用者が過半数を占めていたところ、昨今は借入者の70パーセント超が変動金利を利用しています。
仮に0.3パーセントの住宅ローンを組んで1億円借りた場合、現在なら月々の支払いは約25万円で済む一方、バブル期の7パーセントだと約65万円と40万円もの開きで、25万円程度の支払いでは4,000万円程度しか借りられませんでした。
不動産の「 価格 」だけを比較しても意味がないとは、このような意味です。
またバブル期に住宅を求める向きは、東京23区などとても手が届かなかったため、首都圏なら神奈川・埼玉・千葉などの郊外やさらにその先の例えば高崎や那須塩原・熱海・三島あたりのリーズナブルな価格で購入できるエリアからの「 新幹線通勤 」というスタイルも見られました。
こうして日本全国の多数の地点で不動産価格は上昇し、1990年に日本の土地資産総額は2,000兆円を超えます。一方昨今は「 都心・駅前・駅近 」といったワードに代表される立地が中心で、2022年の歳資産総額は1,000兆円程度と、この30年で半分程度に縮小しているのです。
新築マンション市場についても、2000年代前半の首都圏発売戸数は9万戸程度、総額3.6兆円程度でしたが、2022年は発売戸数3万戸弱と3分の1、総額1.8兆円程度と半減しています。
全国の住宅着工戸数も、やはりバブル期には160万戸超えのところ、昨今は80万戸代と半減です。住宅産業は典型的なデフレ産業だったといえます。
■ 今後のマーケットに影響を与える3つの要因
今後どうなるか予測するのは比較的かんたん。住宅市場に影響を与える要因トップ3は「 金利 」と「 人口動態 」そして「 政策 」で、他は些末な材料と言っていいと思います。
まず「 金利 」。これは、タイミングや幅は不透明なものの、ここまで下げたものは上がるしかありませんから、上昇基調となると観るのが妥当。金利が上がれば不動産価格が下がるのは自明ですね。
次に「 人口動態 」。これも予測は容易で、国立社会保障・人口問題研究所が想定するように、人口・世帯数減がピークを打つ2050年くらいまでは需要減が続くわけですから不動産価格には下落圧力。
「 政策 」はもっとかんたんで、現在の国家予算を支えているのは税収の他、過半は国債発行です。これができなくなる事態。つまり財政破綻や金融リセットが、いつかどこかかのタイミングで起きるでしょう。
ざっくりイメージとしては、戦後の財政破綻で、日本経済の自立と安定とのために実施された財政金融引き締め政策として、後にGHQ経済顧問のジョセフ・ドッジに「 日本の経済は両足を地につけておらず、竹馬にのっているようなもの 」と指摘され、税収の範囲内に予算を収める「 ドッジライン 」と呼ばれた経済合理化政策のようなもの。
早晩、各種の税制優遇を施して、今のように容易に住宅取得ができる状況ではなくなるでしょう。
そんなこんなで大家さんの世界は、かつて地主さんのものだったのがある意味民主化され、サラリーマンでも投資できるチャンスができるようになると同時にコモディティ化してきました。
しかし、今後は一般的な「 会社経営 」と同じような見立てやスキル、志が求められるようになる、いやもうなっていると思いますが、言ってみればよりまともな市場になるだけだろうと思います。
いい時代ではありませんか。
※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。
アクセスランキング
- 今日
- 週間
- 月間
-
-
【東京都23区】積み上がる中古マンション在庫。一方で江東区湾岸エリア・清澄白河駅周辺では在庫の減少が顕著に調査(不動産投資)/その他
-
埼玉高速鉄道線の延伸計画。事業化要請は断念するも実現すれば利便性は高まり沿線の発展に大きく貢献都市計画・再開発(地域情報)/横浜・川崎・千葉・埼玉/首都圏
-
塗装系悪徳業者S君から届いた見積もり。工事開始で気づいた違和感と落とし穴【中編】ガングロ大家/27話
-
150万円の土地と100万円の戸建を売却。「激安で買い、安く売る」でも儲かるのが不動産ふんどし王子/119話
-
金融庁が各金融機関の投資信託パフォーマンスに関する資料を発表。パフォーマンスが優秀な金融機関について解説調査(不動産投資)/金融・融資関連
-
最新の不動産投資コラム
-

仙台物件のキーマンであるお義母さんを、ひろ*さんはいかに戦力化して融資を引いたか【第2回】
- 大家対談/ひろ*さん×5050
-

味のある古民家をリノベーション!改装してペット旅館にしてみる
- らいおん/50話
-

マインドセット!不動産投資家になる前から10年続けた勉強法
- 元公務員大家パスカル/8話
-

東京・札幌・仙台・富山の4拠点で賃貸業を営むひろ*さんと札幌から一時撤退した5050(ゴーさん)が遠隔地物件投資を考える【第1回】
- 大家対談/ひろ*さん×5050
-

大家歴10年、試行錯誤を経て辿り着いた「購入物件」を決める5つのポイント
- アカサカトモコ/24話
-

リスクが増す新築RC投資。破綻した会社の決算書から見えた前兆とは?
- 極東の船長/185話