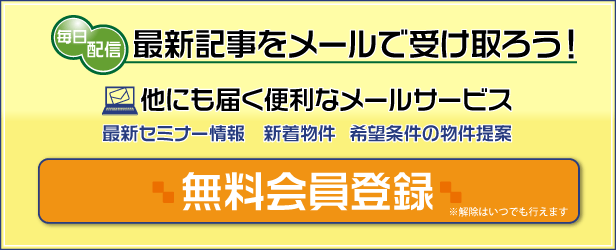今年に入り、4月8日に任期満了の黒田日銀総裁の後継人事が日増しにメディアでも話題になっています。
私の金利予測は、現在の日本の経済状況や産業構造、労働環境に鑑み、短期金利は当面上がらず( 上がってもマイナス金利がゼロになる程度 )、長期金利は緩やかに若干の上昇です。
しかし、金利や金融政策は日銀総裁が独断で決められるものではありません。世界情勢・政府の経済対策・その他いろいろな要因が日本経済に絡んで左右されます。
現在のアーリーステージの不動産投資家さん達は20代から40代の方が多いのではないでしょうか。その層の方たちは、社会人になった時には既に平成バブルが崩壊し、物価はデフレ状態に。そして金利も下がり続けていました。
更に、ここ十年の間に不動産投資を始めた方は、日銀の異次元の量的質的緩和の影響で低金利に慣れ、大都市では不動産価格は右肩上がりでした。インフレ・高金利を知識としては知っていたとしても、肌感覚で自ら実際には経験されてません。
今回は、頭の体操として、仮に政府・日銀が目指す「 良いインフレ 」が実現し、高いレートの借入金利が継続した場合の不動産価格の動きと、インフレ時にこそ不動産投資をすべき理由について話します。
■ 通常は、金利が上がると不動産価格は下がる
いまさらながらですが、金利が上がるとマイホームなどの実需でもアパート・マンションなどの投資でも不動産価格は下がります。
マイホームを住宅ローンを利用して購入する場合、その方の年齢や給与所得から逆算して月々のローンの返済限度額を決められます。金利が上がれば月々の返済額のうち利払いが多くなり、元本返済に充てられる割合が少なくなり、借入可能額が減少します。
賃貸についても同様のことが言えます。家賃水準が現状のままなら、金利負担が増える分、収益が減ります。現在の投資用不動産の価格は収益還元法によって決まることが多いため、収益が減少すれば不動産価格は下がります。
■ 「 良いインフレ 」で金利が上昇すると不動産価格は上がる
インフレとは、物価が上昇基調にある状態です。物価が上がるということは、裏返せば、貨幣価値が下がるということです。
インフレの状態が続くと、多くの方が貨幣価値が下がる前に、お金をモノに換えたり、サービスで使おうという気になり、消費意欲が促進されます。企業も経済活動が拡大しているので内部留保しておくよりは投資していこうという経営方針になりがちです。
「 良いインフレ 」とは、物価が上昇する過程で、多くの方々の給与水準が上がり所得も増え、値上がり分を賄える状態を言います。
日本も良いか悪いか別として平成初めまでは、インフレの状態であることが多かったです。インフレだったことを示す一例として昭和50年代の定額貯金の最高利率は8%と記憶してます。
預金の利率が8%なのですから、借入金利は10%を超えていたこともあります。また、インフレにより貨幣価値が下がるので、現物資産に換えていこうという意識が一般的に強かったです。
当時は、「 不動産価格は下がらない 」という土地神話が信じられていた時代で、資産防衛の観点から日本全国の土地が買われていました。賃貸不動産の表面利回りは1~2%ということも珍しくありませんでした。
さすがに平成バブル崩壊により土地神話が崩れ、収益還元法が定着した昨今では、インフレが継続したとしても、土地神話が復活することはないでしょうね…。
結論として、金利が上がると一旦調整が入り、不動産価格は下がりますが、その後に「 良いインフレ 」の状態になれば、物価に準拠して不動産価格も上がっていくでしょう。
では企業が仕入れ価格や製造費用の高騰分を価格に転嫁できず、給与所得も上がらない「 悪いインフレ 」になった場合はどうなるのでしょうか。
景気がよくならない中でインフレが進行する状況を「 スタグフレーション 」と言います。いまのように金利は上がらないので、不動産価格も金利の影響に限って言えば、現状維持か、建築費の値上がりによる若干の上昇程度になると予想されます。
■ インフレ時の不動産投資のメリット
前述のとおり、インフレ時には貨幣価値が下がります。現預金などの金融資産の価値が下がるだけでなく、負の金融資産=借金の資産価値も同様に下がります。
「 良いインフレ 」時は、不動産の価値が上がり、借入金の価値が下がります。より大きくレバレッジを効かせ借金をして不動産を取得することにより、資産効率が高まることになります。借入金利の水準も上がりますが、家賃水準も上がるため、ある程度はカバーできます。
この時、より良いケースにする方法として、インフレ初期に借入金利を固定金利にすることがあります。金利差のメリットを長期間享受できますので、更に収益性が高まります。
こう書くとインフレ時の不動産投資は良いことばかりのように感じられますが、注意も必要です。平成バブルが弾けて多くの投資家が消えていったように、一転、デフレマインドに戻ると歯車が逆回転します。
今年は特に、日本の産業力・政策・人口動態・投資エリアの成長性・地政学的リスクなどについて、アンテナを高く中長期的に分析し、自分なりの投資判断スキルを養うことが肝要といえるでしょう。
※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。
アクセスランキング
- 今日
- 週間
- 月間
-
-
【東京都23区】積み上がる中古マンション在庫。一方で江東区湾岸エリア・清澄白河駅周辺では在庫の減少が顕著に調査(不動産投資)/その他
-
埼玉高速鉄道線の延伸計画。事業化要請は断念するも実現すれば利便性は高まり沿線の発展に大きく貢献都市計画・再開発(地域情報)/横浜・川崎・千葉・埼玉/首都圏
-
塗装系悪徳業者S君から届いた見積もり。工事開始で気づいた違和感と落とし穴【中編】ガングロ大家/27話
-
鳥取県と米子市が共同しアリーナを整備。2027年4月1日までに供用を始める予定都市計画・再開発(地域情報)/広島/中国・四国
-
大家歴10年、試行錯誤を経て辿り着いた「購入物件」を決める5つのポイントアカサカトモコ/24話
-
-
-
息子を『世界一の金持ち』にする実験‼︎7歳が始めた投資ビジネスとは【前編】ソーリムウーハー/7話
-
埼玉県・所沢駅東口で新商業施設が4月にオープン。周辺市場はファミリー向けが狙い目か都市計画・再開発(地域情報)/横浜・川崎・千葉・埼玉/首都圏
-
【東京都23区】積み上がる中古マンション在庫。一方で江東区湾岸エリア・清澄白河駅周辺では在庫の減少が顕著に調査(不動産投資)/その他
-
2025年に始まる「LPガスへの費用上乗せ禁止」で大家とガス会社の関係はどう変わるのか?【後編】その道のプロ/ガスタンク少佐
-
福岡県内で3店舗目、小郡市でコストコの新店舗が今秋オープン予定都市計画・再開発(地域情報)/福岡/九州・沖縄
-
最新の不動産投資コラム
-

多重債務サラリーマンに、ワケあり賃貸併用住宅の住宅ローンはつくのか!?悪戦苦闘の末、オーバーローンをGET!
- すずまる/10話
-

外国人解禁で民泊売上月70万!新法前から始めた民泊はうまくコロナ期をすり抜けた【第3回】
- 大家対談/ひろ*さん×5050
-

息子を『世界一の金持ち』にする実験‼︎投資家の子育て5つのルール【後編】
- ソーリムウーハー/8話
-

キーパーソンはお義母さん?東京に住む会社員が地方物件を買う為の融資戦略【第2回】
- 大家対談/ひろ*さん×5050
-

味のある古民家をリノベーション!改装してペット旅館にしてみる
- らいおん/50話
-

マインドセット!不動産投資家になる前から10年続けた勉強法
- 元公務員大家パスカル/8話