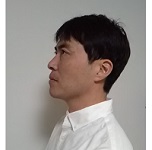オミクロン株という変異株が現れたという報道が盛んです。元々RNAウイルスは変異していくものですし、感染力こそ高まったようですが軽症の人がほとんどという報告も複数あり、大事には至らないように思います。
しかし、延々続くコロナ禍という、コロナウイルスそのものより、政府の過敏反応から至る社会構造の部分的マヒや、思想の分断から大衆間の断絶が起こりつつあるという現象が散見され、そんな事もあってか人々の不安心理はなかなか回復に至らないようです。
依然として、大学生や外国人、若手社会人需要の弱さから、ワンルームの入居率が落ち込んでいます。都心のファミリーマンションは底堅いのにワンルームは空室だらけという、アンバランスな雰囲気の年末となりました。
■ 著名な投資家たちの動き
世界経済に関しては、複数のヘッジファンドマネジャーがハイテク株利食いを進めつつあり、長期的には破局がくるのだろうという懸念を内包しつつ、今はまだリスク資産を保有している様子が開示情報から見て取れます。
スタンリー・ドラッケンミラーやソロスファンドなどはハイテク株をかなり売却していますが、それ以外はさほど大きくは売却を進めていません。
ハイテ...
しかし、延々続くコロナ禍という、コロナウイルスそのものより、政府の過敏反応から至る社会構造の部分的マヒや、思想の分断から大衆間の断絶が起こりつつあるという現象が散見され、そんな事もあってか人々の不安心理はなかなか回復に至らないようです。
依然として、大学生や外国人、若手社会人需要の弱さから、ワンルームの入居率が落ち込んでいます。都心のファミリーマンションは底堅いのにワンルームは空室だらけという、アンバランスな雰囲気の年末となりました。
■ 著名な投資家たちの動き
世界経済に関しては、複数のヘッジファンドマネジャーがハイテク株利食いを進めつつあり、長期的には破局がくるのだろうという懸念を内包しつつ、今はまだリスク資産を保有している様子が開示情報から見て取れます。
スタンリー・ドラッケンミラーやソロスファンドなどはハイテク株をかなり売却していますが、それ以外はさほど大きくは売却を進めていません。
ハイテ...
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる