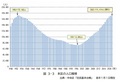JR南武線武蔵新城駅から歩いて2~3分。商店街の一画に明らかに周囲とは違う、ひとつの意思で統一された建物群がある。地元の4代目大家さんである株式会社南荘石井事務所(以下南荘石井)が経営する一画だ。
同社は武蔵新城、武蔵中原、溝の口を中心に22棟、およそ370戸の賃貸住宅を保有しており、そのうちの武蔵新城エリアには地域の公共スペース的な空間もある。そこに2023年5月、新しい建物が誕生した。
共用施設充実エリアに完成した新築物件

新たに誕生した建物セシーズイシイ23は武蔵新城の商店街「はってん会」から少し入ったところにある。
商店街に面しては南荘石井が経営する賃貸住宅セシーズイシイ17があり、その建物の1階、セシーズイシイ23と同じ通りにはカフェ「新城テラス」がある。この建物内の中庭に面した2階には「新城WORK BOOTH」「新城WORK FITNESS」がある。
これは商店街を挟んで反対側にある「新城
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる