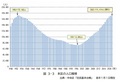「保険のことはプロである保険代理店に任せておけば大丈夫」。おそらくこう考える人がほとんどだろう。しかし、本当にそうだろうか。実は、そうとはいえないかもしれない。なぜそのようにいえるのか、事例を元に解説する。

契約件数上位の優良店に勧められた“間違った火災保険”
ある不動産投資家(以下、Aオーナー)は、自身が所有するRC造3階建ての賃貸マンションにテナントとして入居した保険代理店で火災保険を契約した。その代理店は、全国で契約数や売り上げが上位で表彰されるほどの優良店だった。
ところが、間違った保険プランに入らされたことを、専門家に指摘されたことで気がついた。
Aオーナーの建物は全体の大部分が住居で、1階にテナントが少し入居している店舗併用型住宅だ。火災保険の場合、住居か店舗、どちらの割合が多いかで支払う保険料が大きく異なる。
Aオーナーの場合は前者のタイプだが、契約してしまったのは後者の「店舗総合保険」だった。店舗は火災が起きる可能性が住居に比べ高いと捉えられるため、保険料が割高になるのだ。
店舗併用型住宅の火災保険の場合、住居部分と店舗部分の建物の面積に応じて平均化する「平均用法」が適用される。しかし、平均用法も適用されていなかった。さらに、RC造か木造かなど、賃貸住宅の構造で割安になるものも当然のように加味されていなかった。
Aオーナーが当初契約していた保険は、年あたり約16万円だった。間違った保険に加入していたことに気がついた後、15年間一括支払いの99万円で正しい保険に入り直したところ、保険料は年あたり6万6000円ほどに抑えることができた。年あたり9万4000円ほどを節約できたということは、15年分とすると141万円節約できた計算になる。
Aオーナーの間違った保険プランを指摘した保険ヴィレッジ(東京都豊島区)の斎藤慎治社長は「問題なのは、家主や保険会社、さらに保険代理店ですら、保険の使い方を把握していないことです」と話す。
加害者に対し交渉ができる保険代理店を選ぶ
Aオーナーが正しい知識を持つ保険代理店に乗り換えたことで、得をしたエピソードもある。
Aオーナーが所有する建物は、大手運送会社のトラックに建物名の看板と壁面部分をぶつけられ、割れてしまったことがある。運送会社の過失が明らかだったため、修理費用 60万円を請求した。
しかし、トラブルを起こした運送会社では保有している運送車両台数が多く、膨大な費用がかかるという理由から会社として対物賠償保険には加入していなかった。保険に加入するかしないかは各ドライバーに委ねられている実態があったのだ。
Aオーナーの看板にトラックをぶつけたドライバーも保険には加入しておらず、「支払う」と言いながら3カ月も支払わず放置されてしまった。
そこで、Aオーナーの新たな保険代理店の担当者は、ドライバーに対し交渉を行った。「オーナーの火災保険を利用すれば、その後は保険会社から直接、ドライバーへ修理費用を請求されることになるが、それでもいいか」という内容だ。
保険会社からの取り立てを恐れたドライバーは即座に修繕費を全額支払った。このような交渉ができる保険代理店ばかりとは限らないだろう。
保険代理店ですら火災保険の仕組みを理解していない場合がある
どんな保険に加入するか以上に大切なのは、保険代理店選びだ。保険代理店が火災保険の仕組みを理解していないせいで、本来は保険代理店が対応するべきところ、オーナーが直接保険会社に問い合わせなければならなくなる。
実際に落雷で電気メーターが故障してしまった際、火災保険が適用されるにもかかわらず「保険では出ないから自腹で修理してほしい」と保険代理店に一蹴されてしまったオーナーもいるという。
では、どうすれば頼れる保険代理店を選ぶことができるのだろうか。
自身で5つ程度、「こんなときはどうすればいいか」と質問を投げかけるのが一つの方法だ。その場で答えられなくても、しっかりと調べる担当者なら信用してもいいだろう。しかし、「~だと思います」「~じゃないんですか」など、曖昧な返事をされた場合は避けるのが賢明だ。特約事項と仕組みを正しく理解している保険代理店を選ばなくてはならない。
取材・文:(つちだえり)