
場所を貸すビジネスのひとつに自習室がある。このところ目に付くようになったコワーキング、シェアオフィス以前から存在しており、最近は使い方がだぶる部分もあるが、基本は学びの場。大きな投資をしなくても始められ、会員制で運営すれば収入も安定しそうだが、実際はどうなのだろう。大阪を中心に複数の「勉強カフェアライアンス」を経営する株式会社ARIAの荒井浩介氏に聞いた。
20~30代サラリーマンに大人の勉強場所を提供
自習室と聞くと学生の勉強部屋のように思うかもしれない。そうした形で運営されている場所もあるが、荒井氏が経営する「勉強カフェアライアンス」は20代~30代のサラリーマンが8割を占める、大人の勉強場所。
キャリアをアップさせたい、資格を取得したいと勉強する、意識の高い人たちが利用者の中心で、Wi-Fi、個室のブースも用意してはいるものの、仕事をする場所としては設定してはいないと荒井氏。それでも近年は2割くらい、仕事で利用している人もいる。
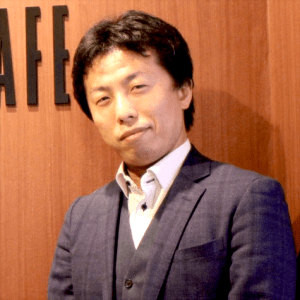
「利用者としては28歳くらいのビジネスマンで、今後のことを考えてキャリアアップを図ろうと、たとえば中小企業診断士などの資格試験のために週に2~3回、終業後に通ってくる人を想定しています。読書、資格試験のための勉強、生涯学習の場としての利用を考えていますが、だからといって仕事をしてはいけないとはしていません。使い方の選択肢はある場所です」。
対象をビジネスマンとしているため、現在はターミナル駅周辺を中心に出店している。出店を決める要因としては交通の利便性に加え、人口が多いこと、教育熱心な層、高所得者層が多い地域かどうかをリサーチするという。
「予備校や自習室がすでにあるような場所ではそういうニーズがあると思われますし、会費支払いができるかを考えるためには世帯収入もポイントになります。ただ、ターミナル駅周辺では最近コワーキングが増えてきており、勉強カフェ本来の目的とは違うものの、使い方では被るところもあるため、今後はそれ以外の立地もあり得るのではないかと検討しています」。
場だけでなく、人間関係も売り
料金はサブスクリプション、つまり月額会員制となっており、フルタイムで利用できるタイプから平日朝だけ、夜だけ、あるいは月に何回利用するかなどで決まっており、平均的には週に2回程度の利用が多いそうだ。
「週に1回以下になると退会率が上がってくるので、使ってもらえるようにスタッフと会員、会員同士の関係構築を心がけています。利用時間としてはあくまで感覚値ですが、1回3~4時間といったところ。終業後にいらっしゃるビジネスマンであればもう少し短い感じですね」。
関係構築という言葉が出たが、この点は勉強カフェの特徴だろう。利用者は入会時の申込書に利用目的を記載することになっており、それを元にスタッフが同じ資格を取得しようとしている人同士を紹介するなど、人が繋がるような仕組みがあるのだ。
「同じ目標を持つ人同士は仲良くなりやすいようで、話が弾み、親友のようになっている人たちもいます。常駐しているスタッフと利用者も顔なじみになっており、挨拶を交わすのは日常です。黙々と仕事だけをするコワーキングなどと違い、人間味があり、カフェっぽい要素もあるのが特徴でしょう」。
近年のコワーキング、シェアオフィスは安さを追求するものか、大手の出資によるラグジュアリーなものに二極化しているそうだが、場だけで勝負、差別化するのは難しい。そこで勉強カフェでは仲間、人間関係というソフトにも力を入れ、他にない場所を目指しているというわけである。
そのため、施設内には会話や食事もできるラウンジと、勉強などに集中したい時に使うワークスペースに分かれている。ワークスペースではパソコンの利用も可能で、物件によってはweb会議や音読にも使える「音読ルーム」も用意されている。
物件選びで成否が決まる
最低限、イケアで机と椅子、パーテーションを買ってくれば始められる自習室ビジネスだが、成功させようとすると意外に難しいと荒井氏。そもそも、最初の物件選びの時点で成否は半分決まっているという。
「最寄り駅から徒歩圏内であることはもちろん、看板が外から良く見えるなど視認性も大事です。入りやすい雰囲気のある建物であること、トイレが男女別に用意されていることなど水回りのきれいさもポイント。
また利用者一人当たりの単価と客数で売り上げが決まるので、そのバランスも大事です。たとえば坪単価2万円で50坪の物件だとすると会費を1万円として最低でも100人の会員を集める必要があります。
実際には家賃以外に人件費その他もかかって来るので、それ以上に集めなくてはいけませんし、こうした場所を貸すビジネスでは一定数を集めるまでには時間がかかります。そうしたことを考えると、もう少しコンパクトな場で始めるほうが賢明でしょう。もちろん、それでうまく行ったら、規模を大きくして行けばよいのです」。
具体的には30~50坪前後で席数で30~60人くらいが始めやすいとも。また、2種類の空間を作り分けることを考えると、部屋の形も見ておきたいポイント。極端に細長いなどの場合、分けにくいこともある。
ちなみに座席数は会員数の5分の1くらいを想定して用意しているとのこと。1日中いる人はそれほど多くはなく、中には仕事が忙しくなったなどの理由で来店頻度が低下する方もいるため、利用時間は意外にばらけるのだ。
不景気に強い、安定ビジネス
立地のリサーチから物件選び、会員募集と時間はかかるものの、比較的初期投資が少なくて済む自習室ビジネスだが、魅力はなんといっても安定感だ。
「大きく儲かるわけではありませんが、一定の会員数がいれば収益の予想が立てやすく、ストック型のビジネスで景気の変動に影響を受けにくいのが特徴です。
逆に東日本大震災、リーマンショックなど社会、経済に変化がある時代には不景気だからこそ、自分の価値を挙げておきたいと考える人がいるのでしょう、自己投資が増え、利用者も増えます。不景気に強い業種といえるかもしれません。
最近はシェアリングエコノミーが知られるようになり、説明しやすくもなりました。それを受けて利用者のすそ野が広がっています。一方で一部、ターミナル駅周辺などでは競争が激化していますが、全体としてはまだまだ少ないため、伸びしろは十分にあろうかと。今後は住宅街なども視野に入れていくべきかもしれません」。
また、ユーザーから直接声が聞けるビジネスでもあり、実際の人との繋がりが多いのがこの仕事の魅力のひとつでもあると荒井氏。スタッフには学生も多く、彼らにとっては人と接することが学びになっているとも。ネット上での関わりとは違う、仕事の喜びがあるというわけである。
コロナの影響は軽微
その上で、注意点をいくつか。ひとつは場作りに費用を掛け過ぎないこと。自習室ビジネスには人の成長に寄与するという社会貢献的な観点もあり、夢を持って始める、こだわりのある人が多いそうで、ついついインテリアその他に凝ってしまう例があるのだという。
もちろん、それを売り上げに転嫁できれば良いのだが、それが可能かどうか、こだわりと売り上げのバランスを冷静に考える必要がある。
もうひとつは入会申し込みはほとんどが検索から来るため、webが苦手という人には向かないとも。現在残っている人はwebに強い人ばかりだそうで、ここでどれだけ人を集められるかが肝になりそうだ。
最後にコロナ禍の影響について。
「緊急事態宣言時は一時減りましたが、逆に今はニーズが増えています。喫茶店、カフェなどで仕事をするにしても時短で20時以降は使えず、長くいると嫌がられもする。旅行には行けないし、時間は余っていますが、その時間をずっと家にいるのも辛い。だから、家以外の場所が欲しいと使っていただくケースが増えています。
遊びには行けないし、遊びに行くとは言えない今日この頃ですが、勉強に行くなら外出の口実になります」。
コロナ禍の影響の少ない業種のひとつといえそうである。
























