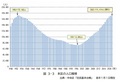ここ数年、サウナがブームだ。だが、まだまだ現状は入口に過ぎないとリノベーション設計デザインを手がける9(ナイン)株式会社の久田一男氏。工事費に補助金を利用すれば利回り50%も可能と聞けば、話を聞きたくなるはずだ。
サウナ人口は推定2000万人
久田氏によると現在のサウナブームは日本に推定で2000万人ほどいる、年に1回以上サウナに入る、セカンドウェーブのサウナ人口がサードウェーブに移行し始めたことで起こったものだという。セカンドウェーブのサウナとはサウナと水風呂の行き来で終始するというもの。
「これでは熱い、寒いの往復でマゾな人なら修業のようで楽しいかもしれませんが、一般の人には拷問のようなもの。たまに出先で入ることはあっても日常的な習慣として入ることはあまりありません。

ところが、サウナ、水風呂の後に外気浴を取り入れると、ここで副交感神経が優位になり、ランナーズハイのようなリラックスできる時間が出来します。これが一般には『ととのう』というもの。一度、この状況を味わうとサウナは最高に気持ちの良い経験となり、繰り返したくなります。これが今、増えているサウナの第三世代です」。
ところが、ブームと社会で話題になり、増えているようであってもまだまだ第三世代サウナは始まったばかりだと久田氏。ブームに対応したサウナがあるのは東京がメインで、あとは地方の有名サウナくらい。まだまだ伸びしろがあり、収益もあげられるというのである。
投資額が少なくても始められる
数自体が少ないというだけでなく、それ以外にもサウナへの投資が有利であると思われるいくつかの理由がある。ひとつはサウナ事業自体は比較的少ない投資で始められるという点だ。

「スーパー銭湯のような温浴施設は最初から設計をしておかないと難しく、ひとつの施設で数億円かかります。改修でやろうとしても業務用の浴槽は重く、普通の商業ビルの場合はかなり大変。ところがサウナでサウナストーブとチーラーと呼ばれる水を冷却する装置があれば、あとは意外に普通の改修で作れます。浴室は普通の家庭用で済むので、ほとんどの建物内に作れます」。
2種類の補助金が利用可能
さらにそこに助成が出る。これには2つあり、ひとつはコロナ禍がきっかけで始まった事業再構築補助金。
「当初はコロナ対策として始まった補助金だったため、売り上げが減少していることが要件として必要で、黒字企業は利用できませんでした。ところが、2023年度から売上等減少要件が撤廃されました。これによってこの補助金が使えるようになった企業、個人事業主も多いはずです。
また、同時に追加要件として市場規模が拡大している業種に取り組むことが加わりましたが、サウナについては市場規模の拡大が望める事業と考えられます」。
もうひとつ、使えるのが昨年から始まった観光庁の「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」。
これは宿泊事業者を含む5者以上の事業者が事業を実施することなどが要件となっており、その地の自治体、観光地域づくり法人などが申請を行う必要があるが、補助金額は改装で1件1億円などと大きい。
「すでに蔵王などが地域で一体となって取り組んでいますが、弊社では妙高にある古いホテルを購入。それでこの補助金を利用する計画です」。
この詳細については後述するが、観光地で経営するなら後者の、それ以外で作るつもりなら前者の補助金が利用できるというわけで、一定の条件を満たす必要はあるが、いずれもそれなりの額が期待できる。その点でサウナ事業にはメリットがあるというわけだ。
外気浴の差別化がポイント
作りさえすれば良いというわけではなく、選ばれるものを作らなくてはいけないという点は賃貸住宅などと共通だ。サウナの場合の差別化は外気浴だという。
「サウナ室自体には差別化要素はそれほどありませんし、湧水が豊富で自然の水を使っているなどで水質、水温などに特徴がある、あるいは浴槽に特徴があるなどの場合は別ですが、水風呂もさほどには差別化しにくいのもの。
ところが外気浴であれば立地その他で十分に差別化できます。たとえば海辺や森の中、山々を見下ろす立地、雪の中その他など。日本の自然を生かした立地を意識すれば差別化はできるはずで、これは日本国内のみならず、世界を市場として見た時にも強みではないかと考えています」。
日本の地方には美しい自然、きれいな水、文化、食があるが、そこにサウナを作ることで世界でも最高のサウナを作れるのではないかと久田氏は考えている。
「日本の温浴施設としてはすでに温泉が知られていますが、温泉は場所によっては肌でその良さ、特徴を感じるのが難しいこともあります。サウナであれば健康志向もあり、リピート利用が期待できます。
今の日本にはグローバルで戦える企業は少なくなりましたが、観光には資源があり、十分に戦えます。そこにサウナを付加すればさらに強い。健康を志向する、富裕層を対象に考えれば投資効果も高くなるのではないかと考えています」。
一泊5~10万円の部屋が1カ月フル稼働


かくいう久田氏はすでに大阪、心斎橋で一泊5~10万円のサウナ付きの宿泊施設を営業しており、競合がないためか、2023年4月で客がいなかった日はわずか1日だけという稼働率である。
さらに2023年5月には東京、北参道でサウナのある宿泊施設をオープンさせる予定。こちらはもともと企業の本社ビルだった4階建てのビルで、1~2階と屋上を借りて2階の50㎡弱を改装、宿泊業で許可を取った。


「長期滞在者を想定、バケーションレンタルで運用するつもりで、かかった改修費は約3000万円。そのうち、3分の2は補助金を利用しました。建物内には寝室とサウナ室、階段を下りたところに外気浴スペースを作り、日帰り利用で3時間3万円、宿泊の場合には期間に応じて1泊9万円から15万円くらいを想定しています。大阪で稼働していることを考えると、十分勝算はあります」。
サウナ単体で作るか、宿泊施設で作るか
ところでサウナといえば、普通は特殊公衆浴場である。ところが、その場合には地域、管轄する保健所にもよるが混浴はできない。男女別にサウナ室、脱衣所、外気浴室などを作る必要が出て来る。
しかし、宿泊施設にするとそうした規制がなくなる。ある程度以上の規模の都市で自然などを活かした外気浴施設が作れない場合にはこの手でサウナが売りの小さな宿泊施設というやり方が良いのかもしれない。

外気浴として使うなら屋上はどうかと考える人もいるはずだが、都市の場合、立地する自治体、保健所の考え方にもよるが、屋上に温浴関係の施設を作ろうとすると、周囲からの視線を遮るような作りが求められることが多い。となると開放感を得られるような施設にはなりにくいのが現状だという。
このところ、サウナ施設の相談がメインになっているというナインだが、6月には大阪難波にあるコンテナを利用した宿を改修、サウナを付加する予定で、その次には大阪谷町の宿の庭を改修、外気浴もできる露天風呂スペースを新設するという。さらに移転後の本社ビルの2階に一般的なサウナ施設、3階に泊まれるサウナ=宿泊施設を作る予定があり、同時期には淡路島の海辺にサウナ付きの一戸建て宿を作るとか。
観光庁補助金はノウハウが必要
その後、来年にはいよいよ妙高の施設の改装も行われる。
「観光庁の助成は事業再構築補助金と違い、1社では申請できません。地域で一体となって再生を考えて取り組んでいるところに参加するという形になっており、妙高ではすでに地元の旅館などの何十軒もが申請しようとしています。弊社もその一部として申請する予定です」。
助成される額は1事業者に1億円がマックスで、全体の改修費のうちの半分から3分の1程度は自前で用意する必要がある。この助成額を考えると、あまり部屋数が多い宿の場合、全室にサウナを用意することはできず、あまり魅力化できない可能性がある。客室数があまり少なすぎてもコスパが悪くなる。
そこで久田氏が選んだのは2500坪の土地に300㎡ほどの建物が3棟、10室が分散して森の中に建つという古い宿泊施設。敷地が広いのでそれぞれの宿泊客がかち合うことなく、ゆったり自然を楽しめる外気浴スペースを作れるはずで、それが最大の魅力になる。観光庁の助成金を利用する際には、どこでやるか、どのような施設を作るかなどにかなり綿密なリサーチが必要ということになりそうだ。
また、観光地ではサウナを使った古いホテル、旅館のバリューアップも手がけており、今も古い旅館で客室を潰してパブリックサウナを作っている。
「建物の前に川がある古い旅館でサウナを作っているのですが、せせらぎを眺めながらの外気浴ができる施設になります。これなら全体が多少古くても、魅力的な宿になるはず」。
賃貸住宅の魅力化にサウナは使えないか
話を聞いていてひとつ、考えたのはある程度の戸数のある、古いマンションのような競争力が下がってしまった物件に付加価値を付けるためのサウナ利用はあり得ないかということ。
実際、この頃、古い社宅等のリノベーションでサウナのついたシェアハウスへの改装をいくつか見た。サウナがあるというだけで入居者には響くだろうし、外に開いた施設にすれば家賃以外の収入を得ることもできる。そんなことは可能だろうか。
久田氏の答えはイエス。
「1階の1部屋をスケルトンにするなどしてサウナ、水風呂を設置、小さくても庭があったらそこを外気浴スペースにしたらどうでしょう。サウナ自体は日本の大手メーカーの品が200万円、300万円で売られていますし、アリババでは品質は不明ですが、20~30万円の品もあります。

ですが、いくつか手掛けてみて分かったのは部屋自体は普通でも、そこにサウナストーブを置けば十分サウナは作れるということ。北参道のサウナ室はごく普通の住宅の仕様となっていますが、全く問題ありません。耐熱ガラスにしないと割れると言われていましたが、いくつか作ってみてそんなことはないと実感しました」。
ただし、ストーブが高い。品質を保証するPSCマークがついた品だと最低でも数十万円。北参道では80万円の品を使っているそうだ。もうひとつ必要なのは水風呂で使う水を冷やす機械でチーラーと呼ばれる。こちらも最低でも30万円くらいから。北参道では80万円かかったという。
「湧水、井戸水を使う場合であれば不要ですが、水道水を使う場合には必須。この2点でそれなりの額がかかりますが、逆にそれ以外はシンプルに部屋をスケルトンにしてサウナ室だけを作り、風呂桶を室内に置くという形でなら比較的安価に作れるはずです」。
ただし、ここでも外の人を入れるとなると特殊公衆浴場の許可が必要になり、男女別トイレなどが必要になる。住宅の競争力を上げるための共用施設として作るのか、外の人にも利用してもらって収益を上げるために作るのか、そのあたりの判断は必要だろうが、サウナ付きの集合住宅、受けそうな気がする。