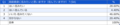近年は「オートメーション」、「スマート」などの文言がホームやオフィスなどに接頭辞として組み合わされ、様々な場面でネットワーク的サービスの中に組み込まれていく流れの中にある。
国土交通省・サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)においても、見えないネットワークの上に一つの端末としての「住宅」が構想されている。そこに恩恵を受ける社会とはどのようなものなのかいくつか最近の話題から考えてみたい

サービス停止されたスマートロック
自分の体験であるが、先日所属している団体の事務所を引っ越しすることになった。多くの人が不定期に出入りする一種のシェア的利用に合わせた鍵管理の問題を考えることになり、スマートロックを各種検討してまずはシンプルなアプリと近接無線通信タイプのものを採用することになったのだが、その検討の中で候補に挙げられていた一社の製品がつい先日、サポート停止というニュースが流れてきたのだ。
サポート停止となったのは、販売後5年になる、買い切りタイプのスマートロックで今後はサービスアプリがアップデートされない、サーバーも更新されないということになる。結果として、ユーザーは次
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる
執筆:(しんぼり まなぶ)