40代前半の木原さん(仮名)がシェアハウス投資を始めようと思ったのが今から8年前。
理由は、戸建てやテラスハウスばかりだと不動産賃貸業の拡大が遅く、いつまでも会社員からリタイヤができないと思ったから。
8年後の今、木原さんは5棟のシェアハウスを自主運営している。
そして、数年前の39歳で念願の会社員からのリタイヤを果たし、専業大家さんになった。シェアハウス以外の物件は、戸建て数件とアパート1棟も所有している。
そんな木原さんだが、開口一番「シェアハウス投資はオススメしません!」ときっぱり。
戸建て投資に比べて利回りは高いが、シェアハウスの自主運営は苦労も手間も格段に多いからだ。
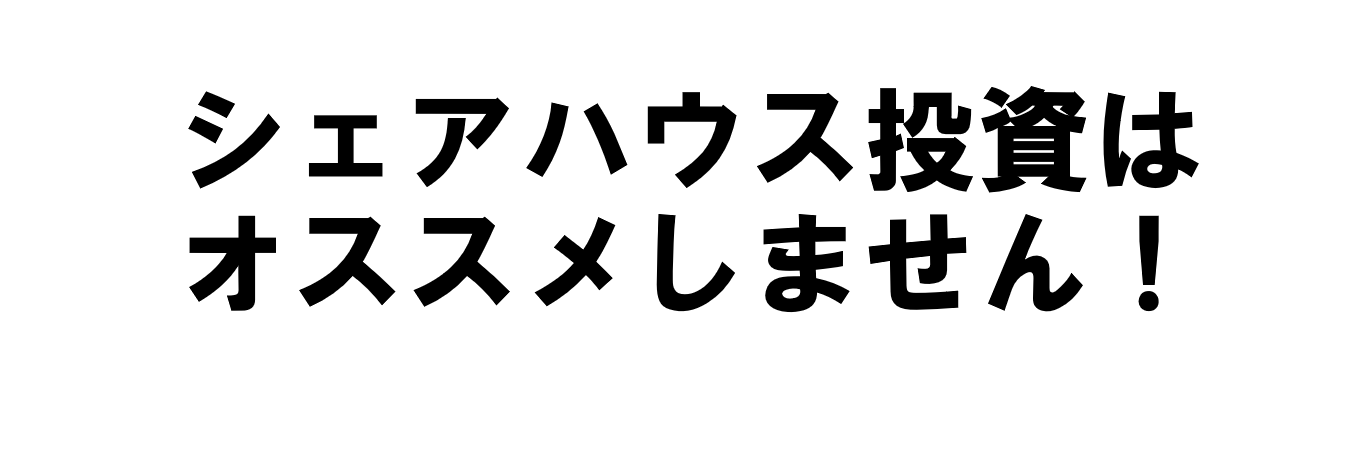
しかし、その苦労ゆえに、運営の楽しさや得難い経験、20%近い高い利回りを叩き出している木原さんに話を聞いてみた。
シェアハウス投資のきっかけは先輩大家さんのブログ
自分にもできるかも!と思った
シェアハウスとは、1つの建物(戸建てなど)内で、入居者はそれぞれ専用の個室を持ち、キッチンやリビング、お風呂、トイレ、シャワーなどを入居者同士で共有しながら住むところだ。
最近はテレビドラマなどでも取り上げられることが多く、若者に人気なのがシェアハウスだ。
木原さんがシェアハウス投資を始めようと思ったきっかけは、首都圏で既にシェアハウスの営むブロガーさんの記事を読んだからだ。
自分もやってみようと、物件探しを始めたそうだ。
ちなみに、シェアハウスが脚光を浴びるようになってきたのが2005年頃。
しかし、人気の高まりで、一部の業者が収益を重視するあまり「脱法ハウス」と呼ばれるような、住むには危険な状態の魔改造も横行し始めた。
そのため、国土交通省よりシェアハウスに関する規制が入った。その後、「かぼちゃの馬車」問題なども起こった。
なお、「かぼちゃの馬車」の建物はリビングルームなどの共用スペースがないので、一般的には「シェアハウス」として分類されない。
2019年に建築基準法改正で、規制の一部が緩和された。
今は、新型コロナウイルスで、シェアハウスは大きな打撃を受けている状態だ。
さて、木原さんのシェアハウスの話に戻ろう。
サラリーマンをしながら兼業オーナーがシェアハウス運営をしている場合は、5~6LDKの一戸建てを購入して、5~6人に貸し出す事が多いようだ。
「運営の効率を考えると、入居者が3~4人だと手間の方が多いと感じます」
一般的に、入居者がシェアハウスを選ぶ理由は、1人で住むよりも家賃が安い、1人暮らしだと寂しい、仲間が欲しい、外国人と出会いたい、など様々だ。
木原さんのシェアハウスも、2019年度のシェアハウス入居率は96%もあったが、コロナ禍では60~70%に落ちているという。
外国人が帰国してしまったことと、インバウンド消滅で民泊からシェアハウスに転用して参入してきた競争相手が増えたことなどが主な原因だ。
「このようにシェアハウスを取り巻く状況は厳しく、運営に手間もかかります。それでもやってみたい場合は自己責任で(笑)」と木原さん。

シェアハウス物件を買う前に「お試し入居」を3ヶ月
自分が住んでこそわかったノウハウや問題点
木原さんがシェアハウス投資に踏み出す前に、「自分でシェアハウスに住んで体験」したそうだ。
新婚だったにも関わらず、妻に同意を得て、1人でシェアハウスに3ヶ月住んでみたという。
平日はシェアハウスから会社に通い、週末は妻の住む自宅で過ごした。
実際に住んでみると、お風呂やシャワーなどの水回りを使用する時間が、あまりかち合わないことに気づいたという。
反対に、家族なら許容レベルの音でも、他人同士が住んでいる場合は音がかなり気になることにも気づいた。
また、間取りの導線が大事なこと、シェアハウス内のイベントがある事で入居者同士の交流が加速すること、入居者選びが非常に重要だということもわかった。
そして、木原さんは2013年に、一棟目のシェアハウス物件を約1,100万円で購入。
大阪市内に建つ6LDK+事務所スペースのある物件だ。2駅からそれぞれ徒歩10分前後だか、住宅地としてあまり人気のある地域ではなかった。
リフォームプランを作るに当たり、木原さんは1階の事務所エリアを有効活用するため、「ものづくりをしたい入居者」を集めようと思いついた。
革細工の職人さんなど、ものづくりをする人達は、音や匂いなどがネックになって工房が持ちにくい。
1階の元・事務所エリアを入居者達が使える工房にし、2階にリビングダイニングとトイレ、3階にお風呂とトイレ、居室は6部屋のシェアハウスへ改装した。
家具家電なども購入し、リフォーム費用と合せて約500万円かかった。

シェアハウス入居者の募集は専用サイトで
ジモティーはハズレが大半だが、たまに大アタリも!
次はシェアハウスの入居者募集。シェアハウス専用サイトで募集するのが一般的だ。
一番有名なサイトが老舗の「ひつじ不動産」。
木原さんは、多くのサイトを試してみた結果、今はひつじ不動産とジモティーの二つで募集している。
ジモティーから応募してくる人は、80%がダメな確率らしい(笑)。入居の問い合わせに対してこちらから返信しても、向こうから返事が来なくなるなどは、よくある事らしい。
しかし、残り20%の割合で良い人が問い合わせてくる場合があるので、侮れないそうだ。3回ほどやり取りして、木原さんは判断している。
どの募集サイトが良いか、また、自分の物件に合うかは様々なので、まずはあちこちのサイトに掲載してみることがお勧めとの事だ。
シェアハウス運営を外注すると、管理料が通常の賃貸よりも高い。だいたい30%ぐらいだ。管理に手間がかかるから。
木原さんはすべて自主管理をしている。
前述したように、自主管理することで、賃貸経営の管理運営スキルが全般的に上がるうえ、問題を起こしそうな入居者を最初から排除することができるからだ。

コロナ禍では対面での面談は難しいが、それでも、なるべく直接会って、入居希望者と話をするようにしているという。
喋っていると相手の「人となり」もよくわかる。遠方の場合は、Zoomなどオンラインも利用している。
契約時には、シェアハウスのルールを厳しく説明するそうだ。木原さんが独自で作った「契約ルールブック」を入居者に渡し、読み合わせもしているという。
ここまですると、入居者も「聞いてなかった」という言い逃れが出来なくなる。入居後も、シェアハウスごとにグループLINEを作り、まめに連絡をしている。
次回は、シェアハウスにする物件の選び方やリフォームのコツ、運営ノウハウの続きをお送りする。
健美家編集部(協力:野原ともみ)






















