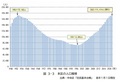公的支援サービスを活用し、香川県高松市内に築55年(当時)の単身向け8戸とメゾネット1戸から成る2階建てRCを購入。大家デビューとDIYデビューを同時に果たすと、大家仲間らと一緒に約2年かけて再生した片山哲也さん。諸経費含め物件価格は1,300万円、修繕費におよそ1,000万円かけたアパートは2023年3月に見事満室となった。

見積りで改修費用3,000万円。DIYで費用を3分の1に圧縮
北に瀬戸内海を臨む自然豊かな香川県高松市のとあるエリアに、赤褐色のタイルをアクセントとしたアパートが建つ。プロによる外壁塗装を済ませ、一新した外観からは放置され荒れ放題だったかつての姿は想像できない。
現在このアパートには地元の人や移住者らが暮らすが、いずれも「この建物だから住みたい」と入居した住人だ。
当時40代だった片山哲也さんがこのアパートを購入したのは2019年12月のこと。


片山さんが中小企業庁による「ミラサポ」を活用し、無償で専門家派遣を受けたのが始まりだ。
「ミラサポ」とは、中小企業、小規模事業者や個人事業主などを対象にした国の支援制度で、経営上の課題について情報交換や相談ができる。インターネット上から会員登録が可能で、登録は無料。最新の経営情報の収集や補助金などの電子申請ができるほか、経営課題解決のため専門家派遣も行っている。
このとき「ミラサポ」に登録の専門家として片山さんをコンサルティングしたのが、DIYや“高齢者向きアパート”などの著書で知られる赤尾宣幸さんだった。
以前、赤尾さんの講演で築古物件を仕入れDIYで修繕費用を圧縮、高齢者に貸すことで高利回りを生んだ事例を聞いていた片山さん。
空き家を再生し、住まい探しに苦労する高齢者に向けて貸し出せば、2つの社会問題を同時に解決できる。「高齢者向けアパート」を事業化したいと考え、今回の専門家派遣を依頼していた。(赤尾さんが「ミラサポ」に専門家として登録していたことから実現した)
ちなみに「ミラサポ」は、片山さんが利用した2019年当時は年3回、無償で専門家派遣が受けられた。交通費も国負担とあって、中小企業や小規模事業者にとって利用しやすい制度だった。
※2022年4月以降は、年5回の専門家派遣に変わり、2回目以降の利用は有償。専門家と委託契約を結び委託料を支払う仕組みとなった。名称も「ミラサポplus」に変更。詳細は「ミラサポplus」内の「中小企業119」のサイトを参照。まずは地域の支援機関に相談を。
「DIYによる空き家活用」と「1階に高齢者の暮らす多世代居住物件への再生」をテーマに、赤尾さんからネットでの物件選びを学んでいたところ、出会ったのが今回のアパートだった。片山さんらはその日のうちに現地へ向かった。
アパートを見るなり「爆裂(※1)もなく施工もよさそう」「私を再生してという建物の声が聞こえるね」と話す赤尾さんに対し、建物にツタの絡まった暗い佇まいから「このアパートが?」と思った片山さん。
よくよく見るとコンクリートの直線的な構成に、柱や梁など日本家屋を思わせる造形。西側の壁面には赤褐色のタイルが位置しており、次第に片山さんも心を掴まれていった。
「安普請ではなく、すごく手がかかっていると感じました。建物価値なしとして、売土地扱いで販売されている物件でしたが、せっかくならこういう面白い建物を活かしたいと思いました」
(※1)爆裂とは―コンクリート内部の鉄筋がサビるなどして膨張し、周辺のコンクリートを破損させてしまうこと
ただ、空き家活用で高いハードルとなるのが高額な改修費用だ。工務店に見積り依頼したところ、電気も給排水も全部取り換えとなり3,000万円はかかるとのことだった。
さすがに3,000万円は無理だと考え、資格の必要な電気工事、漏水リスクのある給排水、外壁塗装はプロに任せることにし、残りはDIYをすることで計画を立てた。
80㎡のメゾネットは、他の単身向け8戸とは異なる意匠が施してあったことから大きな手は加えず、修繕しながら住んでくれる入居者を募集することとし、残りの8戸については1戸あたりの改修費に100万円弱で計算。外壁に200万程度と見積もり、自己資金1,200万円に加え、1000万円の融資を引こうと考えた。
このとき金融機関開拓のサポートをしてくれたのが「香川県よろず支援拠点」の担当者だ。国が中小企業や小規模事業者に向け全国に設置した経営相談機関で、相談は無料。実は「ミラサポ」への専門家支援相談の一次窓口の一つでもあり、片山さんが実現したい事業を担当者は応援してくれた。
信用金庫の紹介を受けた片山さんは「高齢者アパート」の事業性を打ち出した事業計画書を提出した。
諸経費を含んだ購入価格は1,300万円。修繕費として約1000万円を計画。結果、信金による単独融資とはいかなかったが自己資金1,200万円を入れ、信金と日本政策金融公庫との協調融資で500万円ずつ、計1,000万円の融資を引いた。個人での借り入れで金利2.2%、融資期間は10年。修繕費用を含めた利回りは19.8%だった。
2019年12月。この物件のオーナーとなった片山さんは、自身初となるDIYでの再生に挑戦していく。
屋外の給排水管位置の特定に奮闘
片山さんはまず、DIYによる高齢者向けアパートづくりのノウハウを持つ赤尾さんに継続指導を依頼した。赤尾さんからの提案で「DIY体験会」を開催。そこで早くも思わぬ事態に遭遇する。
「DIY未経験の私が大家仲間と共に実地で学べるようにと、赤尾さんが複数回にわたりDIY体験会を開いてくれました。初日に、床がフカフカするという話になり床下を開けたところ、シロアリが過去に発生した痕跡があり、床下の木材が劣化していました。急きょ、その日の工程にはなかった薬剤を撒き、根太も交換しました。DIY初心者にはディープな経験でしたがこんなことも自分でできるのかという自信がつきました」


前述のとおり、給排水管はプロへの依頼となったが、前段階の配管位置の調査については片山さんが行った。これが最大の難所だった。
「屋外は元々地中のどこを通っているのかも分からず、水を流したり地面を掘り起こしたりして一つ一つ調べました。詰まっていた箇所は掃除をし、業者さんに新たに配管し直してもらっています。古い鉛管も残っていたのですべて取り替えました。屋内も室内の至る所に配管がむき出しだったので、業者さんと相談の上、床に配管してもらって、その上から床材を敷きました」
時に大家仲間や業者らの人手を借りながら、物件購入から半年後の2020年6月、1階の1部屋がモデルルームとして仕上がった。
DIYと併行し、片山さんが取り組んだのが介護事業者の開拓だった。地域の介護事業者と連携し、入居を希望する高齢者のあっせんを受けようと考えてのことだった。
赤尾さん指導の下、アパートから車で30分以内の介護事業者で、長く経営している小規模事業者を中心に30社営業した。モデルルームには声をかけた3社の担当者が内覧に来てくれた。



担当者らに改善点があればと尋ねたところ、「よく考えて作っていますね。十分だと思いますよ」と介護事業者からの評価は上々だった。
高齢者に住んでもらうよう営業を重ね、コツコツとDIYを続けた片山さんだが、結果からいうとコロナの時節柄、介護事業者との連携による高齢者の入居はゼロに終わった。
代わりに3人もの入居希望者をあっせんしてくれたのが香川県の移住支援の窓口だった。
片山さん自身、同じ香川県でも徳島県寄り地域の出身で、転職に伴い2013年に高松市に移住していた。市内には江戸時代に高松城の門前町として栄えた古い街並みが点在し、住民主導のまちづくりも盛んだ。まちづくり活動に参加するなかで、ボランティアなどのソフト面だけなく、空き家活用のようなハード面からも地域に貢献できればと考えていた。
そのなかで、近年増えている県外からの移住者にもマッチするかもしれない、と県の移住支援窓口に「短期入居でお試し移住もできる」ことを提案。アパート事業への熱意は担当者にも伝わり、70代の人を含む長期での3人の移住希望者の紹介につながった。
満室となったアパートの自主管理も行う片山さん。介護事業者との連携による高齢者の入居こそなかったが、建物に魅せられた20~70代までの多世代が暮らしており、さながらコミュニティ賃貸に近いという。管理していて大きなトラブルに直面した経験はないと片山さんは話す。
元々IT企業でプログラマーをしていた片山さんだが、空き家再生に関わりたいと脱サラし宅建業を開業。“まちの不動産屋”として活動をしている。「ひとつのものを長く大切に」をコンセプトに古き建物に息吹を与え、次の世代に向けた住まいづくり活動を続けている。
執筆:(すどうみき)