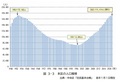ファンドが企業が切り離す不動産の受け皿に
カナダのほかアジア系も最大8000億円を投資へ
日本経済新聞電子版が10月12日に配信したある記事が、不動産業界関係者の注目を集めた。タイトルは「不動産ファンド、日本で1兆円投資 企業売却受け皿に」。
新型コロナウイルスの感染拡大で国内の不動産市況悪化を懸念する声が強まる中、外資系ファンドが「逆張り」するかのように、日本国内での巨額の投資を進めるというのだ。
この動きについて、東京カンテイ市場調査部の井出武上席主任研究員専門家は、国内の不動産投資にとって「順風だ」と断言する。

まず、日経電子版の内容を見ておこう。
日本国内での大型投資に踏み切るのは、カナダに本社を置く大手不動産ファンド、ベントール・グリーンオーク(BGO)だ。
BGOは米欧の年金基金などから資金を集め、アジア対象の新ファンドを設立。ファンドとは別に、大株主のカナダ保険大手なども直接資金を出し、BGOが運用するという。
資金総額は25億ドル(約2600億円)になる見通しとのこと。このうち8割を日本に振り向け、借入金を含めた日本への投資余力は最大100億ドル(約1兆円)が見込まれるとしている。
すでにBGOは2019年、武田薬品工業から大阪市内の本社ビルなどをまとめて取得している。新型コロナの影響で業績が悪化した企業の不要な不動産や、非中核事業である不動産子会社を売る動きが加速し、BGOがその受け皿となる投資を進めると日経電子版は分析する。
また、テレワークなど在宅勤務が広がりつつあるものの、日本は住宅が狭い上、IT関連のインフラも不十分なため、オフィス需要は大幅には減らないとBGOが見ているとは指摘する。
このほか、インバウンド(訪日外国人客)が減ったことを受け、割安になったホテルの取得も進めるとしている。
また日経電子版では、アジア系のPAGが今春に設立したファンドを通じ、今後4年程度で最大約80億ドル(約8000億円)を投じる動きや、カナダの大手投資ファンド、ブルックフィールドが日本に拠点を構え、国内市場への参入を加速している動きが紹介されている。
外資ファンドは東京、大阪などで手堅く投資
衝撃は「新宿三井ビル」売却、不動産切り離し加速へ
この動きについて、東京カンテイの井出氏は「『魅力があるから買われる』という意味では、国内の地価やビル賃料を高く維持する方向に力が働く。企業などによる資産切り離しが始まっている中、買い手が現れることは、日本全体にとってはプラス要因だ」と評価する。
また、外国の投資家は基本的に投資対象の選別が手堅く、リスクが高いエリアで物件を買うことはないとみる。東京、大阪、名古屋、福岡、札幌などの大都市以外には「入ってきづらいだろう」とする。

ちなみに、井出氏は、今後、日本企業が手持ちの不動産、とくに古いビルなどを切り離すなどの動きは、新型コロナやそのほかの構造的な要因で「加速する可能性がある」と予想する。
「古いビルが競争力を失っていく中、建てかえたりリニューアルしたりするより、切り離したほうがいいという判断が出てくるのではないか」
そういう意味で「驚きだった」とするのが、三井不動産が10月9日に発表した、旗艦物件の新宿三井ビルディング(東京都新宿区)の不動産投資信託(REIT)への売却だ。
同ビルは1974年竣工の高層ビル。井出氏は「新宿駅西口におけるオフィスのバリューへの評価なども踏まえたリスクヘッジなのだろう」とする。
日本企業のテレワークへの爆発的な移行はない
急激な空室率の上昇、賃料の下落もなし

ところで、日経電子版にも出ていた、在宅勤務とオフィス需要の関係について、井出氏はどう見ているのだろうか。
井出氏は「今は企業はコロナで緊急避難的にテレワークに移行せざるをえなくなっているが、日本の企業風土を考えると、コロナ後も恒久的なテレワーク導入につながるのかどうか。今のところ、テレワークへの急激な移行が進み、オフィス需要が沈み込むことはないと思う」とする。
最近は、パソナグループが本社機能の淡路島への移転を発表するなどの動きが出ているが、「メガトレンド(大きな構造的変革)化するまでには至っていない。あくまでレアケースだ」する。
今はオフィスの空室が増えているが、テレワークの普及というより、企業業績の悪化で、賃料の高いオフィスから安いオフィスへから移るといった動きが「バイアスとして強い」とみる。
もっとも、「BCP(事業継続計画)の観点から、大都市災害や地震、洪水などへの対策を考慮に入れ、テレワークを恒久的に導入する企業も出てくるかもしれない。そうなると、テレワークへの一定のシフトは起こる」ともみる。
ただ、それを踏まえても、「今の都心のオフィスの数が100として、90か、行っても80までは残るだろう。そういう意味では、テレワークへの爆発的な移行はなく、雪崩を打つように急激に空室率が上がり、賃料が下がるようなことはない」とする。
また、コロナでも痛手をこうむらない大企業などが入る「Aクラス」「Sクラス」のビルは賃料が下がらず、コロナ下で空室が出てもすぐ埋まる可能性が高いが、「雑居ビルで飲食店がたくさん入っているところは厳しい。テナントの飲食店が廃業しても、後が埋まらない」と指摘する。
オフィスビルの間でも「二極化」が進む可能性がありそうだ。
取材・文 小田切隆
【プロフィール】 経済ジャーナリスト。長年、政府機関や中央省庁、民間企業など、幅広い分野で取材に携わる。ニュースサイト「マネー現代」(講談社)、経済誌「月刊経理ウーマン」(研修出版)「近代セールス」(近代セールス社)などで記事を執筆・連載。