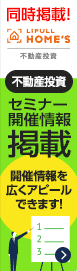10年間に及んだ日銀・黒田体制。異次元の金融緩和を推し進めて市中に大量の資金を供給してリーマン・ショックと東日本大震災により沈んでいた日本経済を刺激した。「円高・デフレ」からの脱却が課題となっていた。黒田総裁が就任する前に1ドル70円台にあったが、現状は130円台になっている。
しかし、当初、2年間で賃金の上昇を伴う物価上昇率2%を目標にしていたが、それが実現できなかった。足元の物価高は円安と資源高によるエネルギー価格の高騰というコストプッシュ型で、賃金上昇を伴う好循環の物価上昇は実現できていない。

長期にわたる緩和マネーは株や不動産に向かった。日経平均株価は、黒田体制の発足時に1万2000円台で推移していたが、一時30年ぶりとなる3万円台に達し、世界が景気後退局面をうかがう今もなお2万7000円台で推移している。
2020年に新型コロナウイルスという思いもかけないパンデミックが発生し、一時的に地価は落ち込んだものの、すぐに戻して不動産取引の価格は高水準で推移している。住宅・不動産業界にとっては蜜月の10年間だったと言えよう。
不動産業界10年間の蜜月は終焉か
ただ、その蜜月がいよいよ終焉を迎え
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる
健美家編集部(協力:(わかまつのぶとし))