前回の記事では、継続した融資を引くためには銀行から高い格付を貰う必要があり、そのためには「債務償還年数」の攻略が不可欠であることを解説した。
そして債務償還年数の計算式は
債務償還年数=
(有利子負債-現預金)÷(当期利益+減価償却費)
であり、この数値が15年、長くても20年を切るようにしておかないと銀行からの格付が悪化し、追加融資が受けられなくなる恐れがあることを認識しておきたい。
今日の記事ではこの債務償還年数を整えるために、我々が何を気を付けるべきかを解説していく。
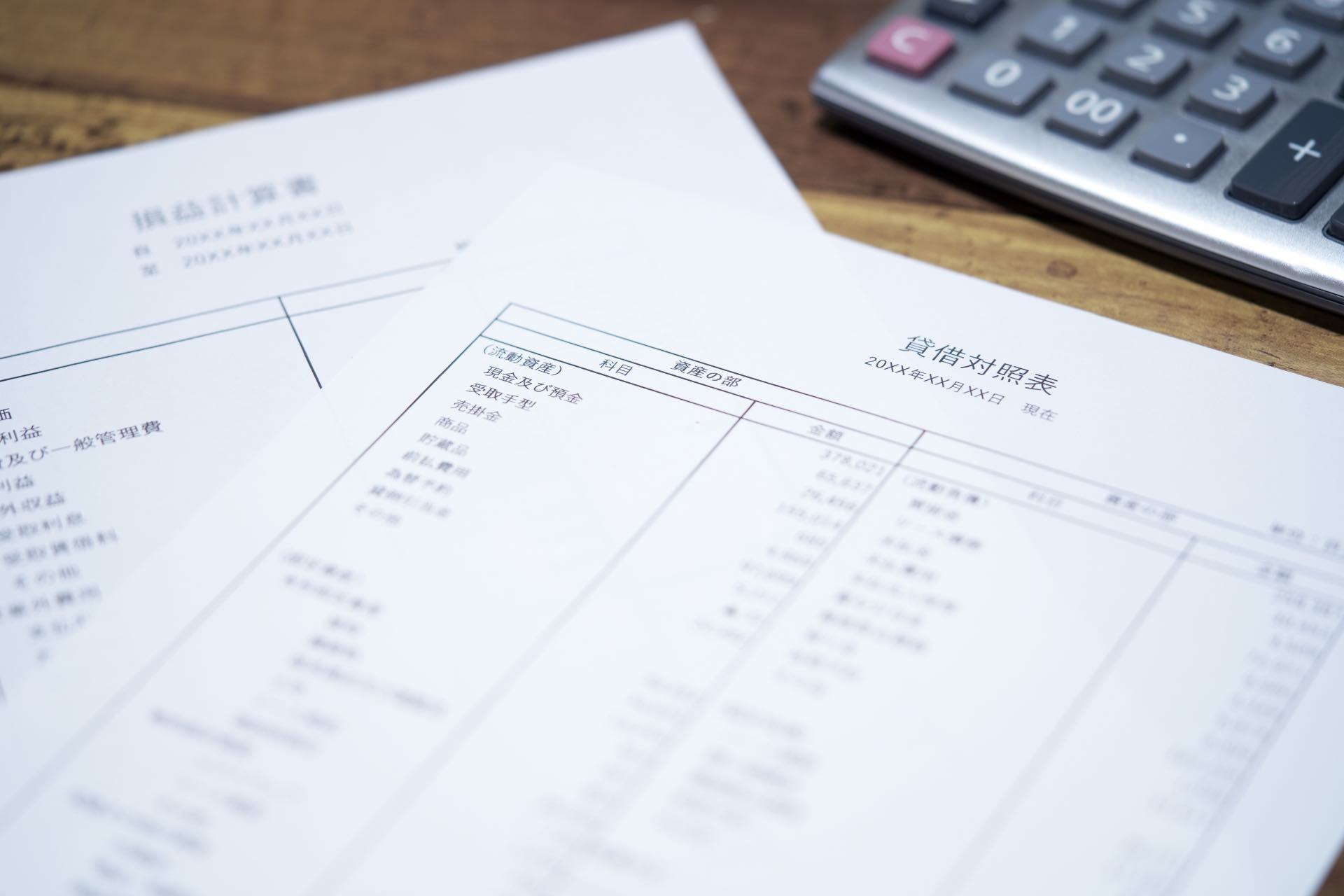
1.融資攻略は節税とは真逆の戦い
債務償還年数に限った話ではないが、銀行が喜ぶ決算書とは、税務署が喜ぶ決算書であることが多い。
銀行は継続的に黒字を出している決算書、そして自己資本が積みあがっている決算書を好む。つまり残念ながら、銀行に好かれる決算書を作るには黒字を出し、法人税等の税金を納めることが必須となるので、納税は避けては通れない道となる。
これは、債務償還年数の攻略においても同様である。当期利益を計上し、抱えている銀行借入をいかに短期間で返済できるか、が良い格付けを得るための方法の一つであることから、数値改善のためには納税は避けては通れないのである。
2.節税と格付、両取りを狙うには「減価償却」の最大化が必須
債務償還年数の攻略において、最も重視したいもの、それは「減価償却費」の最大化である。
債務償還年数の計算式を見れば明らかだが、この数値を改善していくには分母にあたる「当期利益+減価償却費」の値をいかに高くするか、が重要となる。
ここで注目したいのは「当期利益と減価償却費は債務償還年数の計算においては両者ともプラスに働く項目であるが、税金の計算においては相反する項目である」ということだ。
当期利益を計上すれば納税の道をたどることになり、減価償却費を計上すれば節税の道をたどることとなる。本来、節税は銀行評価に悪影響を及ぼす行為になりがちだが、債務償還年数において「減価償却費」という費用の計上はプラスの作用をもたらす行為なのである。
言い換えると、「減価償却費の計上」は銀行の評価を落とさず実行できる唯一の節税方法であるとも言えるのである。
3.具体的に何をするべきか
格付を高めるためには「減価償却」の最大化が有効だと説明したところで、我々は具体的に何をするべきか。
まず全員にお勧めしたいのは「物件購入に関わる諸費用」を資産計上とすることである。物件購入時には、物件価格とは別に、仲介手数料、登記費用、融資手数料、固定資産税按分、不動産取得税など様々な経費が掛かる。
これらの費用を「支払手数料」などの単年の経費に計上するのか、「資産計上」にして減価償却の元にするのかで、同じ経費計上でも銀行への影響は変わってくるのである。
税金の判断が絡むため、この記事では詳細は割愛するが、自身の決算書を締める際には各項目に注意を払い、担当の税理士とよく議論することをお勧めする。
税理士の世界においては「節税こそが正義」と考えている人も多く、銀行への見栄えまで気を配ってくれる人は少ない。ここに気を配るのは、他でもない大家本人の仕事であると言える。
4.まとめ
今回は債務償還年数の攻略のカギとして「減価償却費」の最大化について解説した。
節税と格付の両取りを狙うには、銀行に嫌われない経費である「減価償却費」をいかに積み上げるかが重要で、そのための1つの方法として「物件購入費用の資産計上化」を紹介した。
次回の記事では「債務償還年数編」の最後の記事として、もう一歩掘り下げた内容をお届けする。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
執筆:(はんざわおおや)























