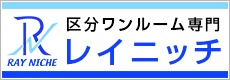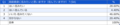今回で3回目となる債務償還年数の記事だが、今回はケーススタディを用いて説明をしていこうと思う。議論したい項目は「中古物件の土地建物比率」である。
不動産賃貸業を進めるうえでは様々な選択を迫られるが「決算書をどうまとめるか?」も重要な選択肢の一つである。前回の記事で説明した、減価償却最大化を得るために工夫すべき重要なポイントとして、「中古物件の土地建物比率」について解説していきたい。
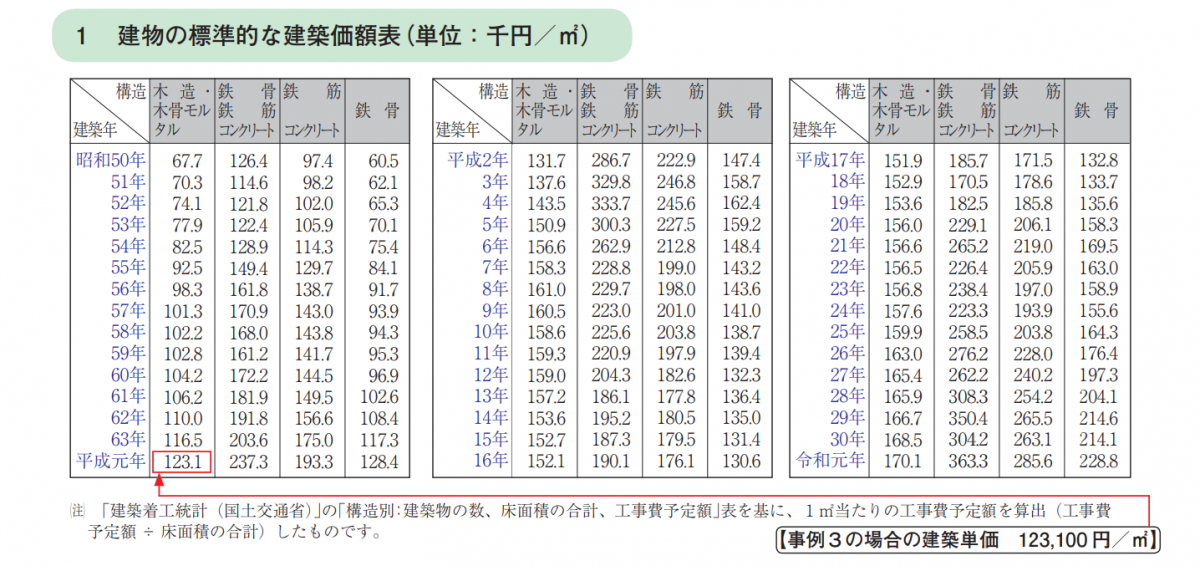
1.物件Aの購入事例について
まずケーススタディとして、仮の物件購入条件を示したい。
―――――――――――
物件概要:重量鉄骨造(1995年築、築27年)
土地面積:1,000㎡
建物面積:800㎡
物件金額:6,000万円
固定資産税評価(土地):2,000万円
固定資産税評価(建物):3,000万円
―――――――――――
今回は、上記の条件を前提として、減価償却費を最大化するために何を行うべきかを解説する。
2.土地建物割合の決め方は様々
上記物件を購入する際に、購入金額6,000万円のうち、いくらを建物として資産計上できるかは重要な分かれ目
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる