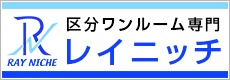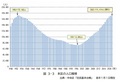家を売却後も賃料払って入居続ける
老後資金を得る方法として人気
政府は2020年度中にも、自宅を売った後も家賃を払って住み続けられる手法「リースバック」について、適切な価格のあり方などに関するガイドライン(指針)をまとめる方向だ。リースバックは、自宅をいかして老後のお金を手に入れる方法として注目が集まっており、政府はルールを整備して〝市場〟をより正常なものにしたい考えだ。
市場がしっかりすればリースバック物件を扱う業者が増える可能性がある。投資家にとっても、入居者を探さなくていいなどのメリットがある、有望な投資先となりそうだ。

政府は昨年12月に閣議決定した20年度予算案に、空き家対策として、戸建て住宅の利用や活用を促す事業の費用3000万円を計上した。ガイドライン作りに必要な費用は、この中から捻出するという。
そもそもリースバックとは、どんなものなのか。
「セール・アンド・リースバック」(賃貸借契約付き売却)とも呼ばれる手法で、家の所有者がその家を不動産会社や投資家に売った後も、売却先と賃貸借契約を結び、賃料(リース料)を支払い
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる