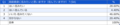東京都品川区と目黒区にまたがる「武蔵小山」。全長約800mのアーケードに210の店舗が軒を連ねる「武蔵小山商店街パルム」を中心に、いくつもの商店街が縦横に連なる買い物や散歩の街として知られる。近年は再開発が進み6月には2棟目のタワーマンションが竣工する予定だ。

駅前の再開発をきっかけにタワマンを建設
「のんべえ」の街からファミリー世帯の街へ
近くには林試の森公園や目黒不動といった散策スポットがあり、週末になると地元住民だけではなく、遠方からも多くの人が訪れる武蔵小山。交通の要は東急目黒線の「武蔵小山駅」だ。1923年に「小山駅」として開業したが、東北本線の同名の駅があったことから翌年には旧国名の「武蔵」を冠した「武蔵小山駅」になった。周辺の町名は小山、小山台、荏原、平塚、目黒本町、下目黒などで、武蔵小山の地名はない。


この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる