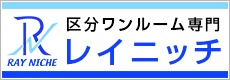不動産業界や資産家、不動産投資家、金融機関などから注目を集めていた「相続マンション評価見直し」で最高裁は4月19日に国税庁が再評価して追徴課税した処分を適法と認めた。
各種報道等によれば、このケースは、東京都と神奈川県のマンション計2棟を2012年に相続した原告人が路線価に基づいて約3憶3000万円と評価し、銀行からの借り入れがあったため、相続税額をゼロと申告していた。
これに対して国税当局の不動産評価額は約12億7300万円と再評価し、路線価による評価は妥当ではないとして約3億円を追徴課税したため争いになっていた。相続する前に故人が購入した価格は約13億8700万円だった。
恣意的な適用 VS 行き過ぎ節税
マンションの相続を巡る税務訴訟であるが、マンションなどの不動産を取得して相続税を節税する方法が一般的なだけに今後の不動産取引に影響が出ないかを懸念する不動産業界の関心は高い。
相続税や贈与税の算出では一般的に路線価を使う。路線価は、国土交通省が発表する公示地価の8割程度とされ、実勢価格よりも低く設定していることで実勢価格との差を利用しての節税対策は広く知られているところだ。富裕層が都心のタ
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる
健美家編集部(協力:(わかまつのぶとし))