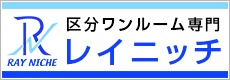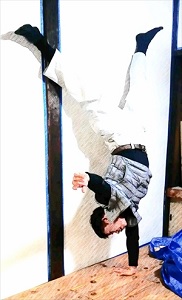安全について色々と書いてきましたが、まだ事故事例の5%も書けていません。建設業とはそれだけ危険な作業を行う業種なのです。アパートや戸建てのDIY現場も同様です。
最終回でも実際にあった事故事例と対策を紹介していきます。知っていて作業するのと知らずに作業するのではケガのリスクも変わりますので、是非目を通していただければと思います。
【 電動工具編 】
1、電動工具で最も危険な丸鋸

回転工具の中でダントツに危険な工具は、丸鋸だと私は思います。実際、以下のような事故事例があります。
・逆歯にした卓上丸鋸で材料と一緒に指先を切断
・手持ち式の丸鋸で刃が材に食い込んだ時に、工具のトルクでキックバック(丸のこが後ろに跳ねる)を起こし、太ももの大動脈を切断、そのまま出血多量で死亡
・切断した時の屑が飛んできて目に入って失明
・手袋を付けたまま作業して、手袋が回転部分に巻き込まれ手首を切断
対策ですが、必ず手袋を外して使用してください。巻き込まれると指がなくなります。また、卓上丸鋸の使用時は、直接手で押さなくていいようにガイドを使用してください。
保管するときも、手持ち式の丸鋸の真後ろに身体を入れないでください。キックバ...
最終回でも実際にあった事故事例と対策を紹介していきます。知っていて作業するのと知らずに作業するのではケガのリスクも変わりますので、是非目を通していただければと思います。
【 電動工具編 】
1、電動工具で最も危険な丸鋸

回転工具の中でダントツに危険な工具は、丸鋸だと私は思います。実際、以下のような事故事例があります。
・逆歯にした卓上丸鋸で材料と一緒に指先を切断
・手持ち式の丸鋸で刃が材に食い込んだ時に、工具のトルクでキックバック(丸のこが後ろに跳ねる)を起こし、太ももの大動脈を切断、そのまま出血多量で死亡
・切断した時の屑が飛んできて目に入って失明
・手袋を付けたまま作業して、手袋が回転部分に巻き込まれ手首を切断
対策ですが、必ず手袋を外して使用してください。巻き込まれると指がなくなります。また、卓上丸鋸の使用時は、直接手で押さなくていいようにガイドを使用してください。
保管するときも、手持ち式の丸鋸の真後ろに身体を入れないでください。キックバ...
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる