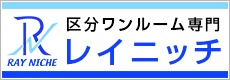気候変動や人口、社会などに対応した
ESG・ SDGsに沿った不動産投資とは?
近年はメディアでもたびたび報じられ、身近になりつつある「ESG」や「SDGs」というキーワード。多くの企業がこれらに取り組み始めているのは、ご存じの通りだ。

言わずもがな、ESGは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉。企業が持続的に成長するにはこれら3つの観点が必要で、2006年にESG投資のガイドラインである責任投資原則(PRI)が定められたことを機に注目され始めた。
簡単に言うと、企業は気候変動や人口問題、ダイバーシティ、企業統治について積極的に取り組み、投資家はこうした企業に投資するという考え方だ。
一方、SDGsは2015年9月に国連がまとめた「持続可能な開発目標」のこと。2030年までに世界で達成すべき目標を「貧困」や「飢餓」「エネルギー」など17のゴール・169のターゲットにわけて提示している。
2001年に国
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる