住宅・不動産業界はインターネットの発達により、不動産事業者と顧客の情報格差が徐々に縮まりつつある。不動産業者としては、この情報格差を一定程度キープしておきたいのが本音だ。
国土交通省は2022年の春に「不動産ID」を本格的に導入した。不動産IDとは、国内の不動産に識別番号を割り振るもので、分譲マンションや戸建て住宅、商業などのあらゆる不動産を17桁の番号で識別する。例えば、分譲マンションの場合、13桁の「不動産番号」と、各住戸の部屋番号など 4ケタの「特定コード」で識別する。
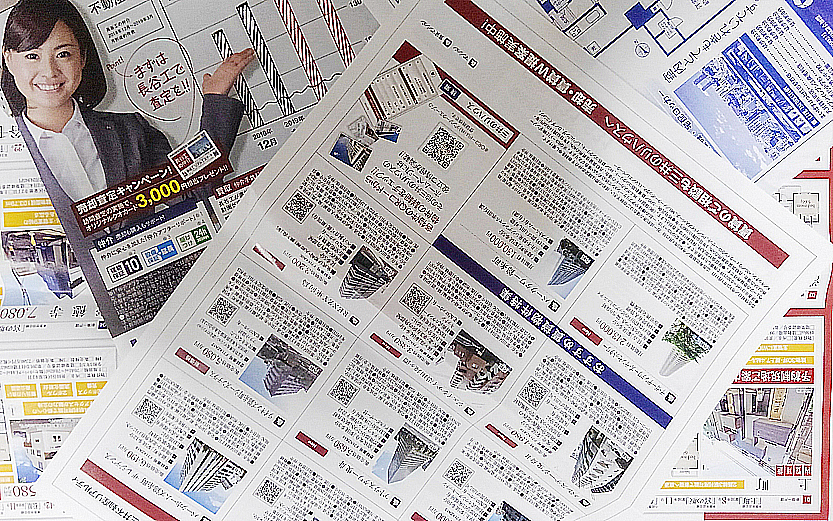
不動産テック業界との温度差
各社の不動産ポータルサイトには同じ物件が掲載されることが多いが、不動産IDで物件情報を整理しやすくなる。国が「不動産ID」の普及を目指す背景としては、中古住宅市場の拡大傾向が挙げられる。スムーズな情報のやりとりが欠かせない。
住宅の間取り図や広さ、リフォーム・リノベーションの修繕履歴などの情報をIDにひも付けることで精度の高い情報の検索・閲覧がスムーズにでき、名寄せによる物件情報の集約がしやすいことで「おとり物件」も排除しやすいことなどに期待している。
しかし、不動産事業者側のノリは今ひとつであ
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる
健美家編集部(協力:(わかまつのぶとし))























