ストリーミングサービスが後押し
大物アーティストの楽曲を運用
株式や債券、不動産など、さまざまな投資対象を運用し、投資家に利益を分配するファンド(投資信託)。投資家は運用の手間をかけることなくリターンを期待できるのが最大の特長だが、近年は大物アーティストの「楽曲」を運用する「音楽著作権」ファンドが注目を集めている。

「音楽著作権ファンド」はその名の通り、アーティストの過去作品の出版権を運用するファンドのこと。
楽曲は著作権の保護期間が終わるまでテレビやラジオからの楽曲使用料、ストリーミング配信サイトからの権利収入が得られ、これを投資家に分配する仕組みだ。
そうであれば、大物アーティストの楽曲を運用する方が運用は有利だが、2018年に創業した英ロンドンを拠点にする音楽著作権の専門ファンド会社「Hipgnosis Songs Fund(ヒプノシス・ソングズ・ファンド)」の場合、投資家から3億ドル以上を調達し、ビヨンセやジャスティン・ビーバーなどのヒット曲を買収。
現在は上場企業としてビジネス規模を拡大させている。基本的には世界的なヒットチャート「Billboard Hot 100」で過去に10位以内にランクインした曲やグラミー賞を受賞した曲の権利を獲得し、中心となるのはポップスとロック。リリースから10年以上経っているが、幅広い世代から支持されている楽曲に投資している。
ファンドとは異なるが、2011年に米国で創業した「Royalty Exchange(ロイヤリティ・エクスチェンジ)」は、楽曲の権利を売りたいアーティスト・パブリッシャーと投資家をマッチングするオークション形式の取引所を運営。過去にはリアーナやJay-Zの楽曲の印税を受け取る権利や「スタートレック」シリーズなどの楽曲の再使用料の一部を受け取る権利を取引している。
アーティスト・投資家の双方にメリット
投資対象として魅力的
なぜ、こういったファンドやプラットフォームが生まれているのか。理由の一つとして挙げられるのが、ストリーミング配信サービスの普及だ。
これにより、時代を問わずヒット曲は多くの人に長く聴かれるようになり、利益をもたらすようになった。また、ストリーミング市場では各アーティストのフォロワーの数から楽曲の再生数を予測することが可能で、将来の利回りも想定しやすい。
かつ、過去のヒット曲は株式や債券などよりも高い利回りを期待することができる。音楽は日常生活に浸透しているので景気に左右されにくく、音楽著作権ファンドを株価暴落時のヘッジ先に使うこともできるだろう。
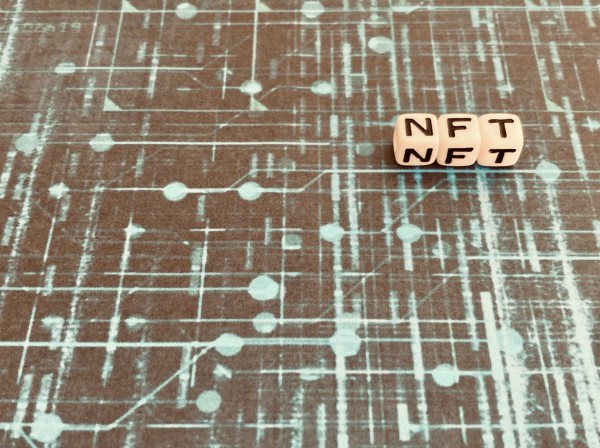
アーティストが楽曲の権利を売却するメリットもたくさんある。
本来であれば将来的に入ってくる印税収入を手放すことになるが、いま高額で受け取ることができる。高齢のミュージシャンの場合、自分がいつどうなるかわからない。残された人生を考えるなら、楽曲を売却して現金化する気持ちは想像しやすい。死後の管理を任せやすい側面もある。
また、一括して権利を売れば、ヒット曲と一緒にそうでない曲も売却することもできる。実際、2020年には『風に吹かれて』などで知られるボブ・ディランが過去の作曲した600曲以上の出版権をユニバーサルミュージックグループに3億ドル以上で売却。昨年12月にはブルース・スプリングスティーンが自身の全作品の権利をソニー・ミュージックに約5億ドルで売却したとわかっている。
音楽著作権を扱うファンドにはミュージシャン・投資家の双方にメリットがあるのが特長だ。
機関投資家が資金を投じる理由も理解できる。今後は個人投資家にもすそ野が広がっていくかもしれない。また、アーティストと個人をつなぐマッチングプラットフォームは投資の面だけはなく、ファンの心をくすぐるサービスとしても面白い。
オンライン上で著作権を扱うには厳重なセキュリティが求められ、ブロックチェーン技術を活用したNFT(非代替性トークン)の普及にも一役買いそうだ。日本でも徐々にサービスは始まっているようだが、ますますの展開を期待したい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
健美家編集部(協力:(おしょうだにしげはる))























