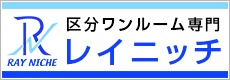最近、取材先で就労継続支援B型あるいは就労支援という言葉を聞くことが増えた。たとえば神奈川県の新築物件の一画にあったコインランドリー、あるいは大阪市城東区の空き家再生で有名な蒲生四丁目(がもよん)ではブルワリーが障害者の就労継続支援の意図を持っているという。
そもそも就労継続支援とは何か?
国は障害を持っている人たちが自立した生活を送るために必要な各種サービスを障害者総合支援法という法律で定めている。
厚生労働省のホームページで障害福祉サービスの概要を見ると大きくは介護給付、訓練等給付と二大別され、さらに訪問系、日中活動系、施設系、居住支援系、訓練系・就労系と書かれた一覧表があり、さまざまな形で支援が行われていることが分かる。
その中にはいくつか就労を支援する仕組みがある。就労移行支援、就労継続支援(A型)、同B型、就労定借支援といったもので、最近注目を集めているのは就労継続支援というものである。
就労継続支援は就労移行支援が「通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの」を対象にした支援であるのに対し、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象にしており、A型、B型の大きな違いはA型が雇用型であるのに対し、B型は非雇用型であるという点。
B型のほうが体調その他に応じて勤務時間等をよりフレキシブルに変更、その人のペースで働けるものとされている。
働きに応じて給料が払われる仕組みを

8月26日にオープンしたクラフトビール醸造所併設のビアレストラン「GAMO4 Brewery」に家主として関わるR-Playの和田欣也氏に聞くとビール製造上の作業としては清掃が多いのだという。

「単純な作業を丁寧にやることが美味しいビール作りには大切で、それ以外にもクラフトビール作りは行程や作業内容が幅広く、多様な人たちの得意が生かせるため、障害者の就労支援に繋げられるのではないかと考えました。
よく区役所のロビーなどで障害者施設の人達が作ったものが販売されていますが、見ていると不当に安いように思えます。クラフトビールのように単価の高い品物を作ることができれば、それによって働く人の給料を挙げることができるのではと思ったのです」。
以前から「がもよん」での活動のうちに福祉的なアプローチをと考えていたものの、飲食店に募金箱を置くようなやり方は重苦しいと考えた。

「そこで熊本地震の時には地域の各店舗が熊本名産のトマトを使ったメニューを考案、それを注文してもらうといくらかが募金に回るというやり方で支援しました。正面から見えるように支援するのではなく、側面支援が良いのではという考え方です」。
築100年以上の長屋を再生

施設には築100年超の5軒長屋を改装。クラフトビール醸造所は人通りの多い道に面しており、外から内部が見えるスタイリッシュな作り。外からはごく普通のかっこいい飲食店に見えているはずだ。

内部にはビール製造に必要な設備のほか、300リットルのタンクが3台あり、ビアレストラン、地域のレストランで提供するほか、いずれは他のレストランからの受託製造、ふるさと納税の返礼品としての利用なども考えている。
運営には社会福祉協議会を通じて知り合った地元で障害者の就労支援を手がけるNPO法人「燦然会」に依頼。現在は福祉事業所以外での就労形態となる「施設外就労」として始めており、いずれは就労継続支援B型事業所、A型事業所に衣替え、さらには一般の企業として成り立つようになればと考えているとか。

支援という意味で周辺の同種事業よりも高めの時給を提示したことで「若干バッシングも受けた(笑)」そうだが、オープン後は順調に滑り出している。
ちなみに関西では大阪市西成区、京都市内などで同様のブルワリーが誕生しており、徐々に知られるように。ブルワリー以外ではコインランドリー、コーヒーロースタリーなどで就労支援を行う例も増えている。
収益も期待でき、社会にも貢献できる
さて、こうした流れを不動産の所有者としてどう捉えるか。
まず、売り上げ。これについては通常の事業所より期待できる可能性がある。
就労継続支援事業所などとして運営されている場合には利用者が仕事をして売り上げる額以外に、利用者数、稼働日数などに応じて国から報酬が支払われることになり、その分は通常の事業所に比べるとプラスになる。
たとえば、ブルワリーの場合、通常の事業所では自分たちで作ったビールの売り上げだけが収益だが、就労支援施設でもある事業所であれば通ってくる利用者に応じたプラスがあるのである。
もちろん、そのためにはサービス管理者、職業指導員、生活支援員などのスタッフを配する必要があり、通常の事業所とは異なる人員配置が必要になる。
施設を作る時点で法に則った建物にする必要があり、そのための出費が嵩む可能性もあろう。建設、運営で通常の事業所にはない出費があり得るかもしれないわけだが、前述の報酬がプラスになることを考えると、それほど大きな影響はないはずだ。
ただし、実際に企画、運営などにあたってはどうしても福祉事業者としてのノウハウが必要になる。「がもよん」の場合のようにすでにノウハウのある福祉事業者などと連携するのが現実的だろう。
ふたつ目は社会貢献という意味合い。関心のない人には無縁だが、大家業は地域密着の仕事である場合もあり、貢献したいと考えている人もいよう。そうした人たちには収益になると同時に貢献にもなるという点で検討しても良いのではないかと思われる。
かつての福祉関連の事業所は作業所然とした、周囲と関わらないものが多かったが、ブルワリーやコインランドリーなどであれば地域の人にも喜ばれるはず。その意味ではダブルで喜ばれる施設になる可能性もあるわけで、関心を寄せてみても良いのではなかろうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
健美家編集部(協力:(なかがわひろこ))