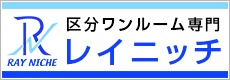大阪の商業地の地価2.5%プラス、3年ぶり上昇
牽引したのは「うめきた2期」周辺で7~8%上昇
2023年1月1日時点の大阪府の商業地の公示地価は前年比でプラス2.5%となり、3年ぶりに上昇に転じた。もっとも、牽引したのは、JR大阪駅北側の再開発エリア「うめきた2期」周辺の「キタ」の地価で、繁華街「ミナミ」の回復は鈍い。
新型コロナウイルス感染拡大前、ミナミの成長はインバウンド(訪日外国人客)への依存度が大きかった反動で、インバウンドの戻りが不十分な現在、地価の上昇に結び付いていないのだ。キタとミナミの地価の「回復格差」は当分続く可能性があり、大阪周辺での不動産投資を考える投資家は、注意してみていきたい。
大阪府の商業地は昨年の公示地価ではマイナス0.2%だった。だが、今年はプラス2.5%と、大きなプラスへ転じた。
その大阪府で目立ったのは、「うめきた2期」近くのエリアの地価上昇だ。

たとえば、大阪市福島区福島6丁目では8.0%、同福島7丁目では7.8%、同吉野1丁目では7.7%と大きな上昇を記録。大阪市北区でも大淀南1丁目で7.4%、同野崎町で7.2%、同中崎2丁目で7.0%と大きな上昇を記録した。
さらには、大阪駅周辺でも3.1%の上昇を記録している。
背景にはあるのは、うめきた2期の再開発が進んでおり、周辺のマンション需要やオフィス需要が強まっていることだ。
うめきた2期は、大阪・関西万博の開幕が予定されている2025年春にはほぼ完成する予定で、大規模な都市公園やホテル、商業施設、企業などが整備される。総面積は9ヘクタール以上に達する。
うめきた2期にある大阪駅の新しい地下ホームも3月に開業したばかりで、関西国際空港と和歌山方面を結ぶ特急などが乗り入れるようになり、関西の交通の結節点としてその役割を増大させている。
うめきた2期周辺ではマンション、オフィス需要続いて拡大
ミナミは回復遅れ、道頓堀・心斎橋は0.0%、日本橋マイナス
うめきた2期の近くでは、すでに不動産投資用の物件の人気も高まっており、その人気が地価を押し上げている側面がある。うめきた2期で働く人の賃貸需要や、関連する企業のオフィス需要は周辺でますます強まる可能性があり、うめきた2期近くの物件を狙う戦略は賢明だろう。
一方、回復が遅れているのが、難波、心斎橋などの「ミナミ」の地価だ。
2021、22年はミナミの8地点の地価の下落率が全国ワースト10にランクインしていた。23年は全国ワースト10から抜け出したものの、戻りは鈍い。
大阪市中央区の道頓堀近辺で0.0%、心斎橋近辺も0.0%と、いずれも横ばい圏内だ。日本橋近辺ではマイナス1.4%と、依然としてマイナス圏に沈んでいる。
理由は、コロナ前の地価上昇がインバウンドの頼りすぎたものであったため、インバウンドの完全には戻らない現時点では、地価の回復につながっていないことだ。この点、国内観光客の戻りが大きい京都などとは異なる点だ。

コロナ前のミナミのインバウンド偏重に怒りの声
国内観光客の呼び込みも不動産投資需要回復のカギ
ミナミの商業施設がコロナ前、あまりにインバウンド偏重だったことに対しては、地元の日本人からいまだに怒りの声が漏れる。
「コロナ前、ドラッグストアなどの商業施設は、店舗内の便利な場所にあるレジをインバウンドだけに開放していた。日本人は、離れた場所や2階などの一部のレジに追いやられていた。
そのときの怒りがあるので、コロナでインバウンドが来なくなって経営が苦しくなった商業施設を、地元の日本人客が店で買い物して助けようという動きがまったく出なかった」
ミナミの飲食店経営者は、こう振り返る。コロナでドラッグストアなどがつぶれ、空き店舗になったことがミナミの地価を押し下げる要因になったのだが、日本人の「応援団」があらわれなかったこともそれを後押ししたといえる。
とはいえ、最近、ミナミでは大勢のインバウンドの姿が見られるようになった。休日の道頓堀周辺など、外国人の観光客でいっぱいだ。宿泊業者によると、インバウンドの宿泊者数はまだコロナ前の水準に達していないという。しかし、4月には中国からの旅行客に対する水際対策が緩和されるなど、インバウンド受け入れの日本の態勢は着々と固まりつつある。
果たして、今後、どこまでミナミにインバウンドが戻り、国内観光客も引き込んで、地価上昇、すなわち不動産投資の需要が強まっていくのか、注目したい。
取材・文:(おだぎりたかし)